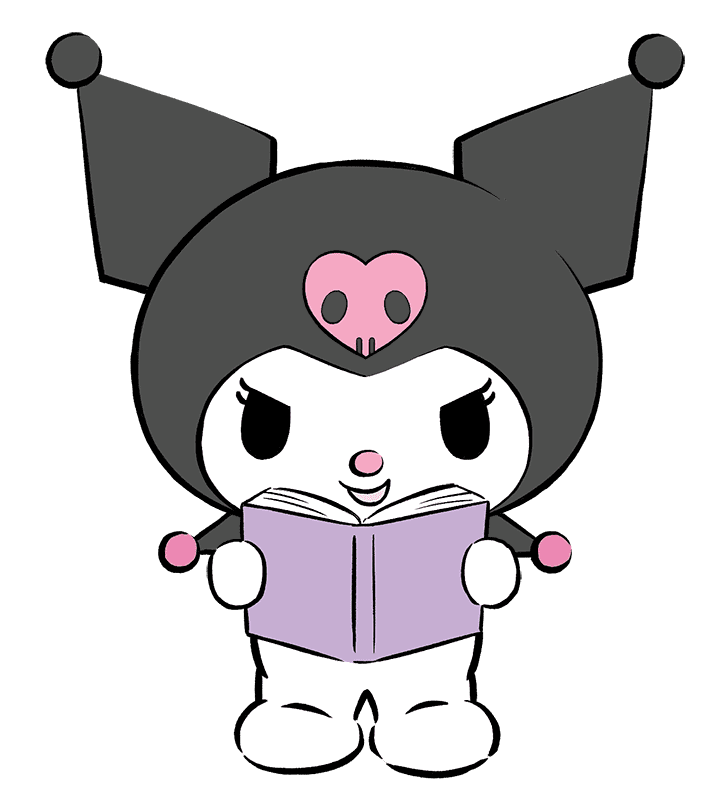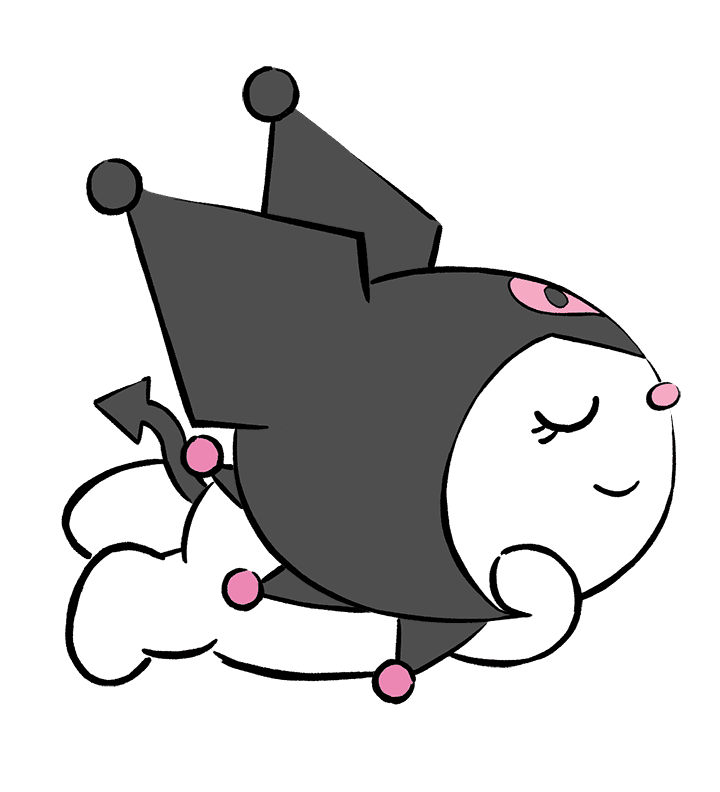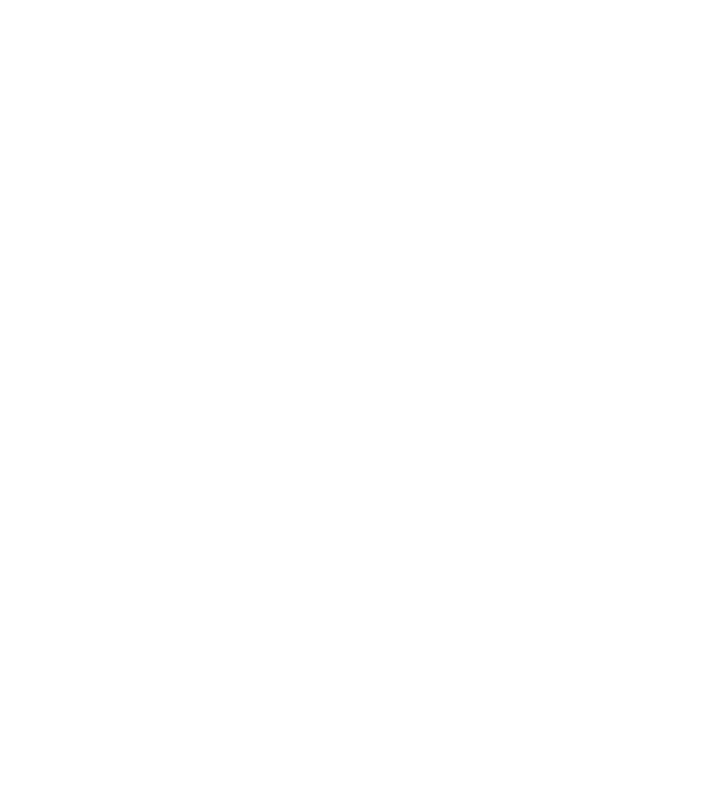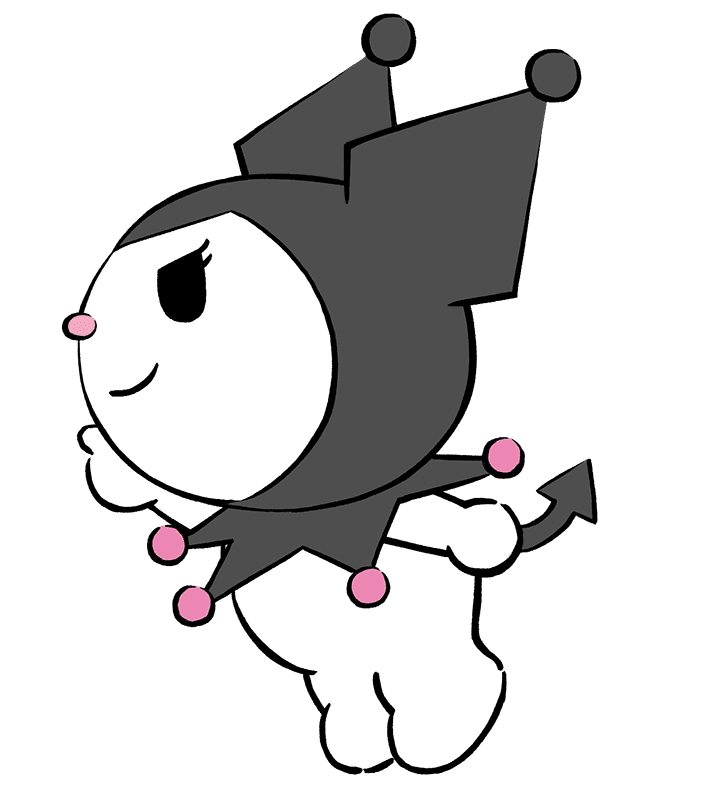はじめて漢方ガイド
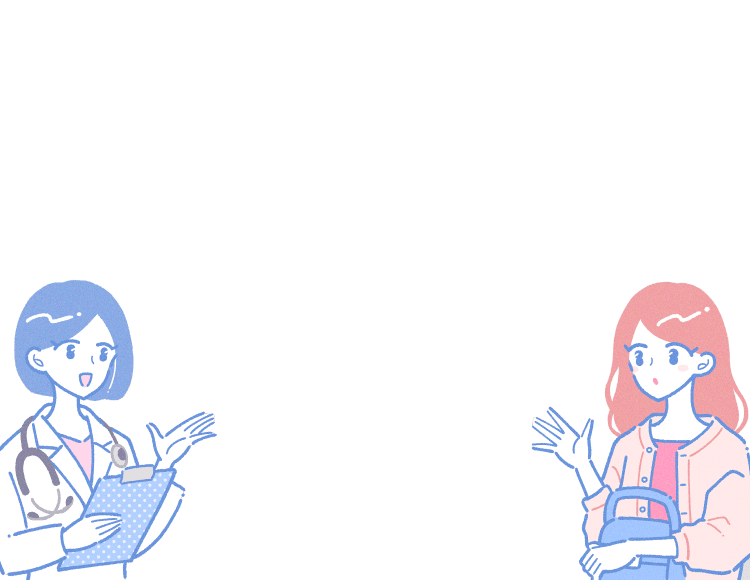
みんなの疑問にこたえます!
漢方Q&A
-
月経に関する悩みは、基本的にどんなことでも相談して大丈夫です。「月経痛がつらい」「周期がバラバラ」「出血が多い・少ない」「月経前に気分が落ち込む」「不正出血かどうか?」「月経のときに冷えやだるさが出る」…いろいろありますよね。
中には、子宮筋腫や子宮内膜症など、治療でよくなる病気が隠れていることもあります。
気になるときは、医師に早めに相談してみてください。 -
「どのくらいつらいか」感じ方は人それぞれですが、「生活に支障が出るレベル」になったら受診したほうがよいでしょう。
例えば、「市販薬が効きにくくなってきた」「仕事や学校を休むことが多い」「症状が強くなってきている」「痛み以外にもつらい症状がある」…などが目安になります。 -
漢方薬は「自然のちから」を活かして、身体のバランスを整えるお薬。もとは中国から伝えられたものですが、日本で独自に発展した「日本の伝統医学」です。「生薬(しょうやく)」という植物の葉や根っこなど、薬効を秘めた自然の素材を組み合わせて作られていて、一人ひとりの体質や症状に合わせて処方されるのが特徴。
不調の「根っこ」にアプローチして、じっくり整えていくイメージです。 日常的に感じやすい不調症状をはじめ、月経に伴う症状にも使われることが多いです。 -
西洋薬は「症状をピンポイントで抑える」のが得意。例えば、熱が出たら解熱剤、咳が出たら咳止めとそれぞれの症状に対応したお薬を処方してくれます。
一方、漢方薬は「全体のバランスを整える」ことを大切にしています。同じ「頭痛」でも、人によって頭痛が起こる原因も体質も違うから、その人に合った処方が必要と考えます。いわば、「いまの自分の状態」全体をケアしてくれるお薬。目的や症状によって使い分けるのが基本です。 -
サプリメントと似ているように感じる人もいるかもしれませんが、漢方薬は病院で医師に処方される「医薬品」です。
サプリメントはあくまで「栄養補助食品」といって、あくまでも食品の一つ。漢方薬は国の基準をクリアした生薬を組み合わせて作られていて、医師に診てもらうことで、自分に合った薬を処方をしてもらうことにつながります。 -
ポイントは「いまの症状」だけでなく「体質」に合った漢方薬を選ぶこと。例えば、同じ腹痛でも冷えて痛い人とお腹が張って苦しい人では、処方される漢方薬が違います。
自分の体質や生活習慣、ストレス状態など、トータルで判断するのが漢方の考え方。だから、「なんとなく合いそう」で選ぶよりも、まずは病院で相談してみるのがいちばんの近道。
医師に診てもらうことで、自分に合った処方が見つかります。 -
たしかに、漢方薬は「じんわり効く」イメージがあるかもしれません。ある程度続けることで変化が見えてくる漢方薬もありますが、速効性を期待して使われるものもあります。例えば、こむら返りや胃もたれ・胃痛などの症状に使う漢方薬は、比較的早めに症状が改善するといわれています。すぐに症状を軽くしたいときも、医師に相談して、自分に合った処方を出してもらいましょう。
-
「自然のものだから安心」と思われがちですが、副作用のリスクもゼロではありません。発熱、息切れ、咳、息苦しい、だるい、発疹、腹痛、むくみ、筋肉がつっぱるなど、不調を感じた場合は、すぐに飲むのをやめて医師に相談しましょう。
複数の漢方薬を服用するときは、副作用が起こりやすい生薬を重複して服用していないか、特に注意が必要です。だからこそ、自己流で使うより、医師に相談して処方してもらうことがおすすめです。 -
煎じ薬(水で煮出して濾した液を飲む薬)は、独特のにおいや苦みがあることも。ただ、多くの漢方薬は、顆粒状や錠剤など、いくつかの種類があります。自分の体質に合った漢方薬なら「服用しにくい」とは感じない場合もあるようです。漢方薬によっては甘味や酸味を感じるものもあります。どうしても飲みにくいなと思ったら医師や薬剤師に気軽に相談してください。
-
むしろ病名の診断がついていなくても、本人が感じている症状があれば、治療の対象になるのが、漢方の強み。例えば、月経前のイライラ、月経中の下腹部の不快感、冷え、むくみ、だるさなど、検査では異常が出ないけど、「なんだかツライ…」という症状に対応できるケースも少なくありません。
漢方薬は生薬をうまく組み合わせることで、症状が出た部分だけでなく、身体全体のバランスを整えてくれます。 -
同じ名前の漢方薬を構成する生薬の組み合わせは一緒ですが、医療用漢方製剤は医師の診察のもと使われるのに対し、一般用漢方製剤は消費者の判断にゆだねられるため、効能効果、用法用量が異なっています。
-
現在、日本では保険診療で使用できる漢方薬が148種類あり、約9割の医師が使用していると言われています。*日本漢方生薬製剤協会の2011年の調査より
-
医療機関で漢方薬が多く処方されるのは、高齢者と女性との調査結果がでています*。多くの女性が悩まされている症状のなかでも、月経痛や不妊、更年期障害や更年期症状、冷え症、イライラ、不眠、気分の落ち込みなどのメンタル症状、胃もたれや食欲不振、便秘などの胃腸のトラブルなどに漢方薬が使われています。この他にも、性別年齢問わず、風邪や疲労倦怠感、便秘、頭痛など様々な症状に対し、一人ひとりの体質に合わせて漢方薬が処方されています。*「第3回NDBオープンデータ」(厚生労働省)に基づき当社作成 医療用漢方メーカー上位100品目で算出
漢方について
もっと知る
監修医師
梶山 広明 先生
名古屋大学大学院 産婦人科学 教授
産婦人科学、婦人科腫瘍学が専門。
女性の生涯にわたる活躍と健康を願って、女性医学の発展に奉仕している。西洋医学と東洋医学のよいところをハイブリットさせた診療に取り組んでいる。