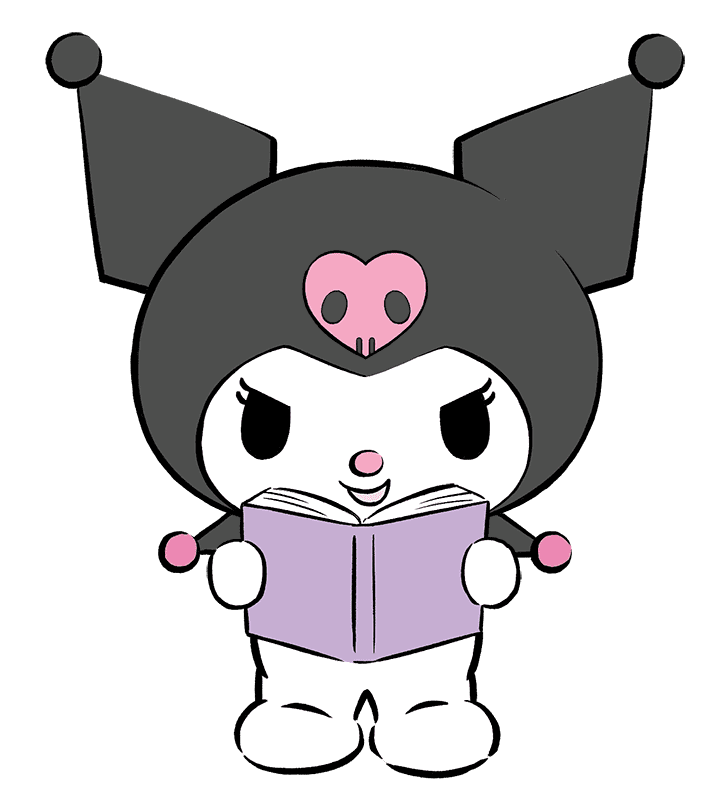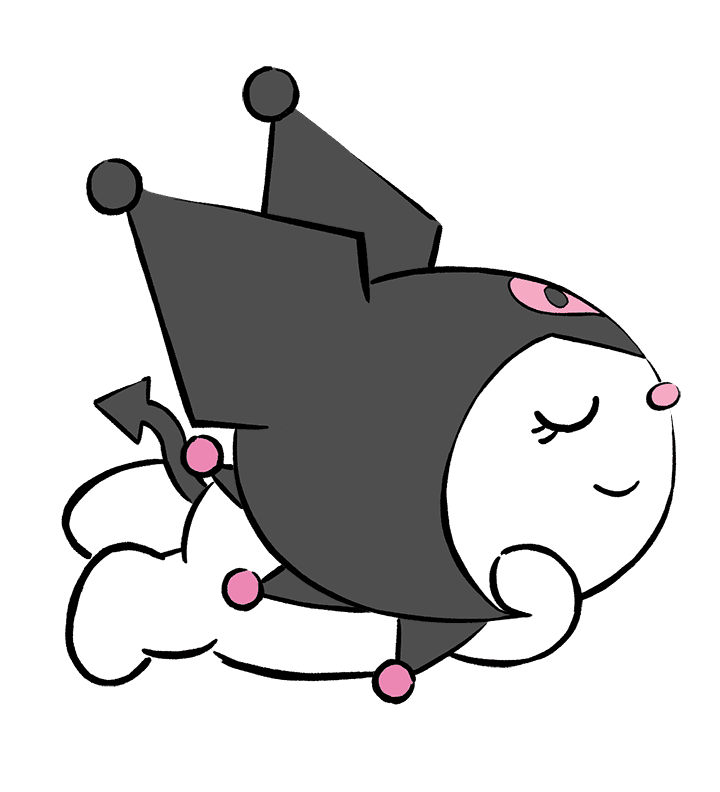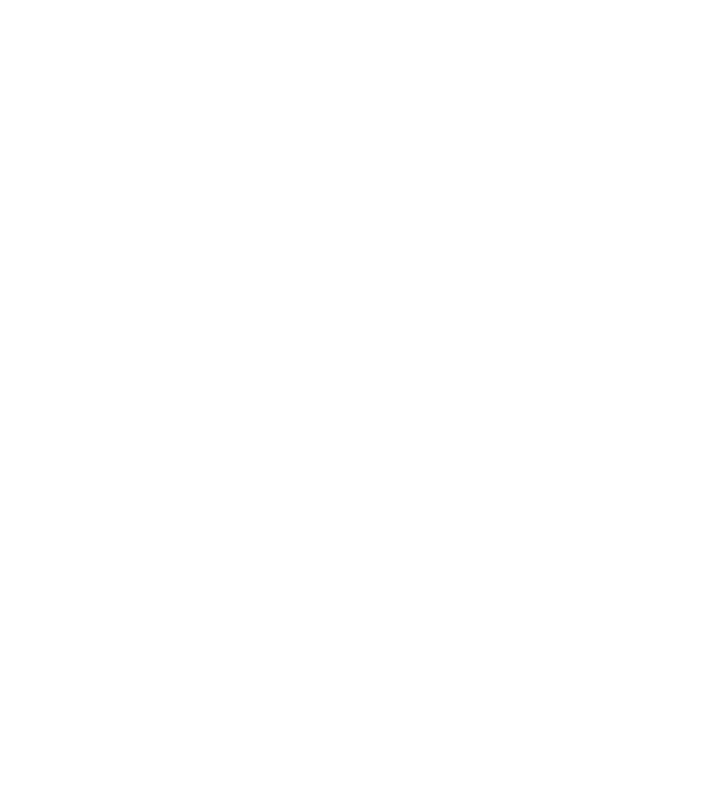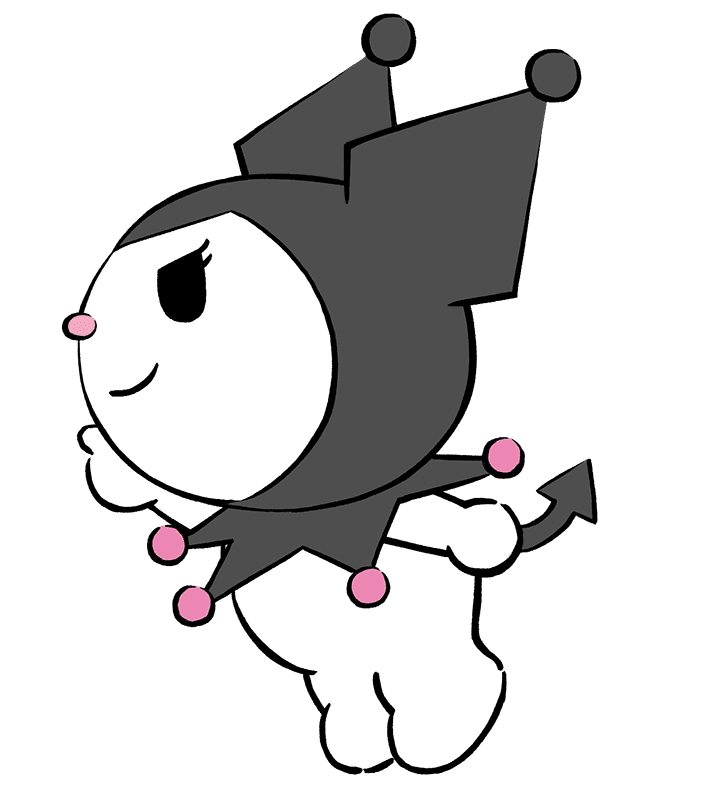月経前や月経中の不調はさまざまあり、どのような症状が生じるのかは人それぞれ。このくらいは、あたりまえかもしれないと思っていたことも、場合によっては病気が関わっていることがあります。
気になる症状や病名をチェックして、少しでも症状に悩むことがあれば、婦人科の診療にあたる医師に相談してみましょう。
生理に伴う
さまざまな不調
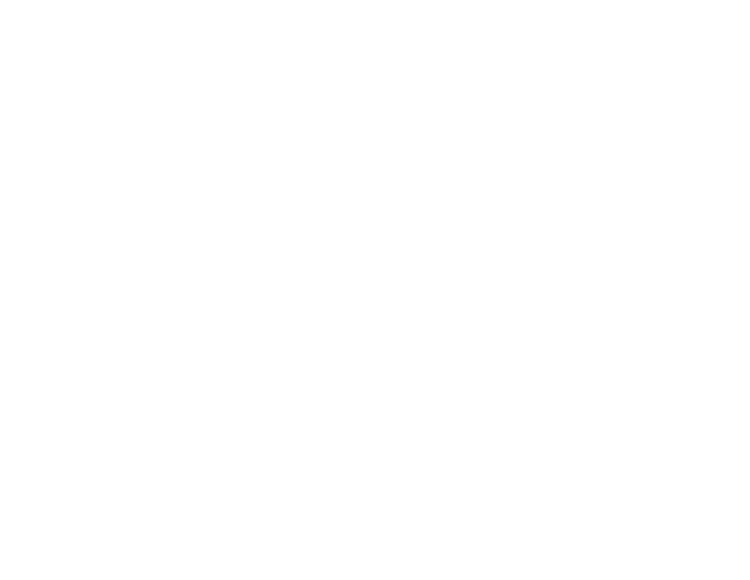
生理が原因で起こる
月経前や月経中の不調はさまざまあり、どのような症状が生じるのかは人それぞれ。このくらいは、あたりまえかもしれないと思っていたことも、場合によっては病気が関わっていることがあります。
気になる症状や病名をチェックして、少しでも症状に悩むことがあれば、婦人科の診療にあたる医師に相談してみましょう。

月経のときに、腹痛や頭痛などが生じることを「月経痛」と言います。症状や程度は人それぞれですが、8割以上※の人が経験するといわれています。日常生活に支障がある場合は「月経困難症」と呼ばれ治療が必要となります。
出典:厚生労働省「働く女性の健康課題とその対策」月経中に子宮を収縮させる「プロスタグランジン」という物質が体内で多く分泌されることが原因といわれています。子宮内膜症や子宮筋腫などの病気が関係する場合もあります。
鎮痛薬で痛みの原因となる物質「プロスタグランジン」が増えないようにしたり、女性ホルモンのバランスを整える薬などで女性ホルモンの変動をやわらげたりします。病気が原因の場合は、その治療を優先します。また、体質や症状によっては、その人にあった漢方薬が用いられます。
漢方医学では、月経痛は血(けつ)の流れの不調によっておこると考えます。血の流れを整える漢方薬を用いることで、痛みだけでなく、冷えやだるさなどいろいろな不調が改善することもあります。
月経中は骨盤内の血の流れが悪くなりやすいので、体を締めつける服装は避けましょう。入浴やストレッチで体を温めるとラクになります。しっかり睡眠をとり、無理せず休むことも大切です。

月経の3〜10日前から、イライラ、頭痛、むくみ、気分の落ち込み、眠気、便秘などの精神的症状、身体的症状がでるが、月経が始まると消失するのが特徴です。女性の多くが大なり小なり経験していますが、程度や感じ方には個人差があります。
はっきりとした原因はわかっていませんが、月経前に女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンのバランスが大きく変わることが関係していると考えられています。この変化にストレスや疲れ、睡眠不足が重なると、症状が強く出やすくなるといわれます。
女性ホルモンのバランスを整える薬などが用いられます。心(精神)の症状が強いときには、抗不安薬や抗うつ剤などが、腹痛や頭痛などには鎮痛薬、むくみには利尿薬、不眠には睡眠薬など、症状に合わせて薬が処方されます。また、体質や症状によっては、その人にあった漢方薬が用いられます。
漢方医学では女性ホルモンの変動に伴う症状を「血の道症(ちのみちしょう)」と呼びます。イライラは気(き)つまりエネルギーの流れの異常=気逆(きぎゃく)・気滞(きたい)、むくみや冷えは水(すい)の異常=水毒(すいどく)、便秘や肩こりは血(けつ)の流れの異常=瘀血(おけつ)とされ、症状に応じた漢方薬が用いられます。
PMSの症状日記をつけると、どんな症状がいつ頃、何日続いているか把握でき、医療機関でPMSを診断する際にも役立ちます。また、生活サイクルや栄養バランスのよい食事をとるよう見直す、体を冷やさないよう衣類を工夫しリラックスする方法を見つけることも大切です。

「PMDD」は、PMSの中でも、特に気分の落ち込みやイライラなどの精神症状が強く、仕事や人間関係など日常生活に大きく影響してしまうのが特徴です。月経のある女性の多くがPMSを経験するといわれていますが、PMDDは全体の約3~8%※と報告されています。
出典:厚生労働省「働く女性の健康課題とその対策」はっきりした原因はわかっていませんが、月経周期の排卵後に増える女性ホルモン「プロゲステロン」の変動が関わると考えられています。このプロゲステロンの量の変化が大きいことで、気分の落ち込みやイライラが生じるといわれています。
PMSと同様に、女性ホルモンのバランスを整える薬が用いられます。症状に応じて抗不安剤や抗うつ薬、睡眠薬などが使われることもあります。頭痛には鎮痛薬、むくみには利尿薬など、症状ごとに対応します。また、体質や症状によっては、その人にあった漢方薬が用いられます。
PMDDは気分の落ち込み等、精神症状が強いことが特徴で、漢方医学では気(き)つまりエネルギーの流れの不調と考えます。頭痛や便秘、むくみなど体の不調を伴うことも多いため、一つの薬で複数の症状に働く漢方薬が選ばれることも。体質や状態に応じて、西洋薬と一緒に用いられる場合もあります。
精神的な症状は、ストレスや疲れで悪化しやすいもの。日ごろから心身に負担をかけない生活を意識しましょう。特に月経前は、睡眠をたっぷりとって無理はしないで。一日の終わりはお風呂でリラックスし、カフェインやお酒は控えめにしましょう。

正常な月経周期は25~38日。25日未満や39日以上、月経周期がわからない場合は、女性ホルモンのバランスがくずれていたり、排卵に問題がある可能性があります。月経不順や無月経を長期間放っておくと、将来の妊娠に影響したり、閉経後に骨粗鬆症のリスクが高くなる可能性があります。
月経周期や期間、経血量は体調や環境で変わることがありますが、長期間上記の範囲から外れる場合は注意が必要です。原因はさまざまですが、女性ホルモンの分泌量の問題や子宮・卵巣・甲状腺の病気、ストレスや過度のダイエットが影響していることもあります。
病院では、子宮や卵巣の状態を調べる検査を行います。月経不順の原因を探り早期の妊娠を希望するか否かを確認後、低用量ピル、女性ホルモン剤、排卵誘発剤などで治療します。また、体質や症状によっては、その人にあった漢方薬が用いられます。
漢方医学で月経不順は、血(けつ)の流れに、気(き)つまりエネルギーや水(すい)のバランスの乱れが加わった状態ととらえています。体調を考慮したいろいろな漢方薬が用いられます。
ストレスの軽減、規則正しい食生活、睡眠を十分にとること、腹部を中心に体を冷やさないことを心がけましょう。

「過多月経」は月経異常の一つで、1回の月経で総出血量が140ml(乳酸菌飲料2本分ほど)を超える場合とされています。昼でも夜用ナプキンが必要、レバー状の大きな血の塊が混じる、8日以上続くなどがサインです。鉄欠乏性貧血になり、めまいや動悸、息切れを伴うこともあります。
ホルモンバランスの乱れや子宮の病気が原因になることも。子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮内膜ポリープ、子宮内膜症などのほか、子宮頸がんや子宮体がんが関わる場合も。甲状腺疾患や血液疾患など内科の病気が影響することもあります。
検査や問診で原因を調べ、病気があればその治療を行います。必要に応じて女性ホルモンのバランスを整える薬、女性ホルモン剤、貧血がある場合は鉄剤で治療されます。また出産経験があり今後の妊娠を望まない場合には子宮内に小さくてやわらかい装置(子宮内黄体ホルモン放出システム:IUS)を留置して5年間月経量を減らすことも可能です。体質や症状によっては、その人にあった漢方薬が用いられることもあります。
漢方医学では過多月経は血(けつ)の異常が関わると考えます。ストレスや疲れで心身のバランスが乱れると血の流れも悪くなり、月経に影響が出ることもあるため、血の流れを整えたり補ったりする漢方薬が用いられます。
まずは生活リズムを整えて、ストレスをためないように。無理なダイエットは避け、規則正しい食事と睡眠を心がけましょう。軽い運動や深呼吸で体をほぐし、リラックスするのもおすすめです。おなかまわりは冷やさないように気をつけて。

「不正性器出血」とは、月経の時期以外に子宮や腟からの出血があることをいいます。茶色っぽい血液が少量つく、鮮血が出る、おりものに血が混じるなど量や色はさまざまです。少量でも1か月以上続く場合には病気が見つかることもあるので、自己判断で放置しないことが大切です。
原因はいろいろ。ホルモンバランスの乱れや排卵期の月経的な出血であれば心配ありませんが、感染症による炎症や子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮内膜ポリープや卵巣の病気、子宮頸がんや子宮体がんが関わることもあります。
検査で原因を調べ、その結果に応じて治療が行われます。大きな病気がなければ、女性ホルモン剤でホルモンのリズムを整えたり、止血剤で出血をおさえたりすることも。貧血があるときは鉄剤で治療されます。また、体質や症状によっては、その人にあった漢方薬が用いられます。
漢方医学では不正出血は気(き)つまりエネルギーの不足や血の流れの異常によって起こると考えます。休養してエネルギーを補い、体を温め、軽い運動で流れを整えるケアがすすめられます。体質に応じて気や血の流れを整える漢方薬が用いられます。
ホルモンバランスはストレスの影響を受けやすいもの。リラックスできる時間を積極的に持ちましょう。十分な睡眠とバランスのよい食事を意識しましょう。20歳を過ぎたら年1回の婦人科検診を習慣にし、月経に関するつらい症状があれば我慢せず早めに治療を開始して月経にふりまわされない元気な生活をおくりましょう。
漢方について
もっと知る
監修医師
梶本 めぐみ 先生
関西医科大学総合医療センター産婦人科/漢方専門外来
産婦人科専門医と漢方専門医の知識を活かして、西洋医学と東洋医学それぞれの良いところをひきだす治療をめざしている。