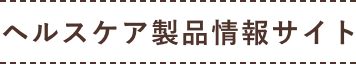漢方の歴史
5〜6世紀ごろ

5〜6世紀ごろに中国医学が伝来し、それから1400年以上かけて、日本で独自に発展した医学が漢方医学です。

〜平安時代

日本に医学が伝来してから平安時代までは、宮廷医が医療を行っていたので、位の高い一部の人しか治療を受けられませんでした。

鎌倉・室町時代

この時代のお坊さんは、医療を広めるために、多くの弟子を持ちました。

江戸時代

鎖国で様々なものが日本化されました。漢方医学も、医学校が設立され、医書が活字印刷されると、日本全土に広がっていきます。

明治時代

明治維新後、新政府は「西洋医学」を国の医学の中心とすることを決めました。

明治〜昭和時代

しかし、一部の医師や薬剤師、薬種商などの間で、
漢方は、脈々と引き継がれていきました。

1950年〜

日本東洋医学会が設立。漢方エキス製剤4処方が、初めて保険適用に。
1976年に38処方、1984年に148処方となりました。

2004年〜

全国80大学の医学部で漢方医学教育が実施。
現在では、約9割の医師が漢方薬を処方しているという調査結果が出ています。