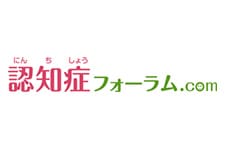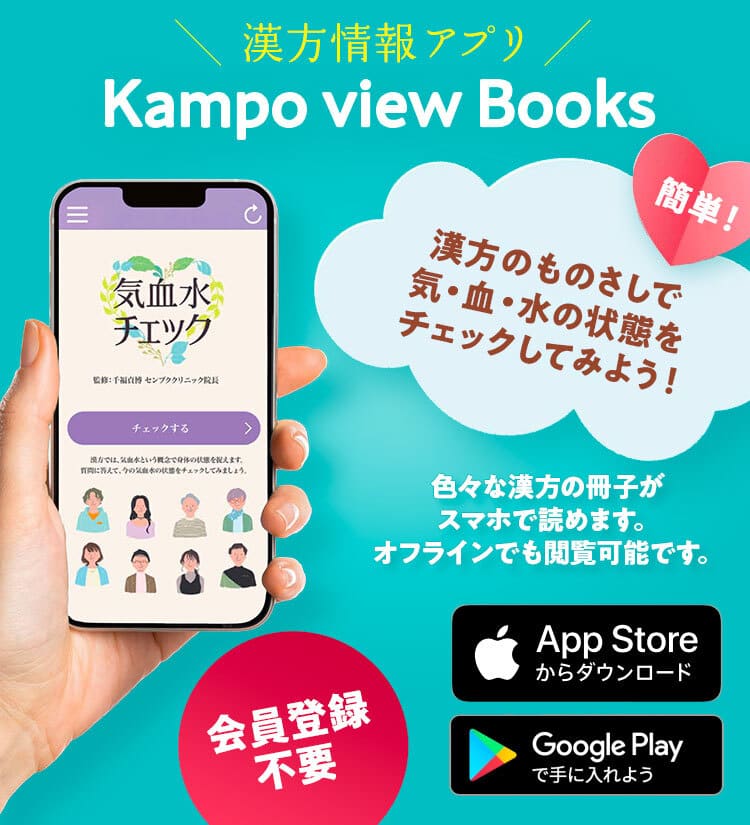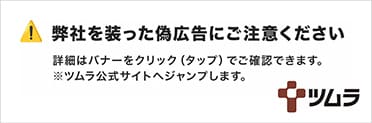今、あらためて脚光を浴びている「サウナ」。
近頃では、サウナ愛好家を“サウナー”と呼び、サウナによる体感を“ととのう(整う)”などと表現するほど、その熱は高まっているそうです。
また、このコロナ禍でもサウナを楽しめるようにと、野外のサウナや一人で楽しむソロサウナなども増えてきています。
人々を次々と虜にしているサウナですが、健康によさそうなイメージはあるものの、具体的にカラダにどのような影響を与えているのでしょうか?
今回は、薬剤師である筆者が、サウナがもたらす健康効果について解説します。
サウナの魅力は、ズバリ「温熱効果」!
私たちのカラダには、深部体温が38度以上になると「ヒートショックプロテイン」という、傷んだ細胞を修復したり、睡眠やストレスをコントロールしてくれるタンパク質が出始めます。 とくに、フィンランドのサウナスタイルである“ロウリュ”は、カラダが温まりやすく効果的だといわれています。 ちなみに、40度の湯船に20分入浴した場合でも、ヒートショックプロテインの発現は確認されているそうです。
今回のテーマであるサウナのメリットはなんといっても、その「温熱効果」でしょう。 カラダが温まることで全身の血管が拡張し、血流がよくなります。これは、疲労回復などに期待が持てます。 また、お風呂と違って水圧がかからないため、純粋に温熱効果だけを得られるので心臓に持病のある人や年配の人にとっても安心です。

さらに、サウナ室には携帯電話やパソコンなどを持ち込めないため(デジタルデトックス)、余計な思考がストップされ、瞑想に近い状態となり、リラックスしやすい状況をつくり出すことができます。
サウナを楽しむ際の注意点として、体調がすぐれない時やケガをした後、食後やアルコール摂取後などは控えるようにしましょう。
温冷交代浴を繰り返すことで、“ととのう”!
サウナで温まったカラダを水風呂でクールダウン、そして外気浴…これが推奨されているサウナの楽しみ方とされています。
さて、サウナと切って切り離せないのが「水風呂」の存在ですが、この時カラダの内部では一体どのような変化が表れているのでしょうか。
じつは、サウナでカラダが温まっているときにカラダ深部では血流が低下し、熱を冷ますために体表の血流が増えている状態になります。
その直後に、水風呂へ入ると今までと逆の現象が起き、深部の血流量が一気に増えていきます。
その際に、血行不良による不調などが改善されていくとされています。
そして、“熱い”と“寒い”を繰り返す(温冷交代浴)ことで自律神経が大きく揺さぶられ、次第に副交感神経が優位になるタイミングが訪れます。
これを“ととのう”といい、頭がリラックスしスッキリする状態になるとされています。
ただし、この温冷交代浴は刺激が強いため、持病のある人や体力に不安のある人は、無理のないように行うようにしてくださいね。
漢方薬でもカラダのメンテナンスを
このような理由から、自律神経を整え、血行促進に期待ができ、心身ともにリラックスできるため、サウナを利用する人が増えているのだと思います。 しかし、感染症の不安だったり、なかなか時間が取れなかったりなどして、サウナに行きにくい場合には、漢方薬でカラダのメンテナンスをしてみるのもオススメです。
漢方薬の中にも、自律神経の乱れによる不調の改善や血行促進に期待できる処方があります。 また、精神的に落ち着かない時や睡眠の質が落ちてきている時などには、サウナとの併用も有効な手段だと思います。心身ともに弱っている時には、ぜひ取り入れてみてくださいね。 その際には、これまでお伝えしているように持病などに注意する必要があるため、少しでも不安がある人は専門の医師や薬剤師に相談してください。

May 26 2021
薬剤師・大久保 愛
関連コンテンツ
Keywords
- 温活
- 自律神経
- 血流