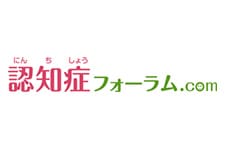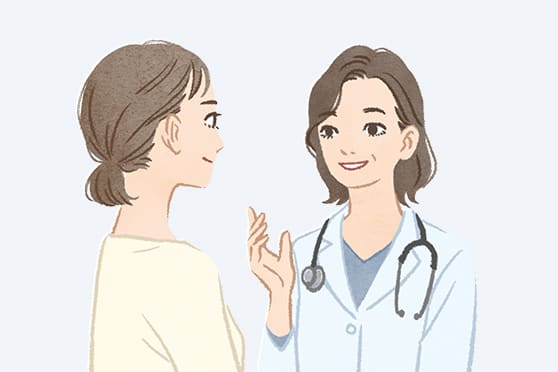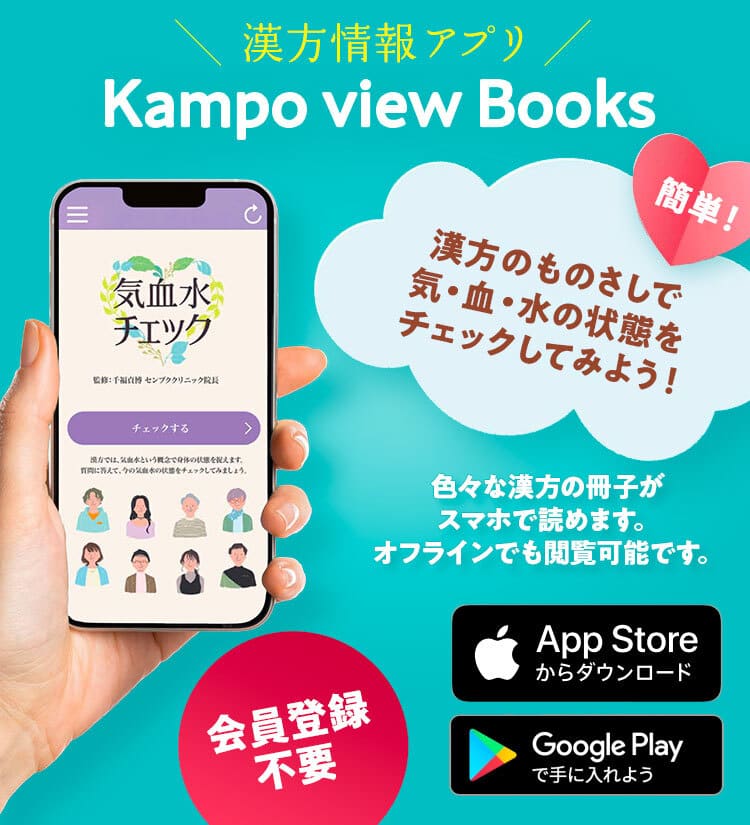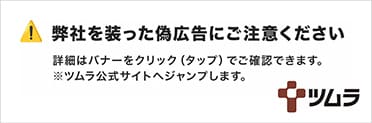歩いていたらつまずいた、疲れやすくなった、以前より食事の量が減った……。年をとったなぁと感じるのは、こんな不調が出てきたときではないでしょうか。「しかし、こうした不調の多くは適切な対策を取ることで改善できるのです」と話すのは、国立長寿医療研究センター理事長の荒井秀典先生。
日本の平均寿命を考えると、40代、50代はまだまだ折り返し地点。「年だから……」とあきらめず、できることから始めていきましょう。荒井先生にフレイル対策のポイントなどについてお話をうかがいました。
Index
加齢による不調は「対策」できる時代に

若いときの話になりますが、日々の診療で高齢者の患者さんを診ていると、多くは治療が必要な病気がある方でした。しかし、なかには「疲れやすい」「眠れない」「食欲がない」といった症状があるにもかかわらず、原因となる病気が見つからない方が、かなりの割合でいらっしゃいました。
当時、これらは「加齢による変化だから仕方ない」と思われていたのですが、21世紀に入って、加齢に伴う変化には「可逆性がある(元に戻ることができる)」「対策ができる」ということがわかってきて、現在の「フレイル」という概念が登場しました。
日本はご存じのとおり、世界に名だたる長寿国です。それをなし得たのは、魚を中心とした食事(いわゆる和食)と、誰もが体調が悪いときに病院に行ける国民皆保険制度などのおかげです。
ですが、国民の皆さんにもっと元気で長生きしてもらうためには、病気を治す・悪化させない仕組みだけでなく、元気に年をとっていくための早期からのフレイル対策が大事になります。
「フレイル」という用語が誕生したいきさつ
私がフレイル対策に関わり始めたのは、2013年ごろ。多くの国民にこのフレイルという概念を広めるため、ワーキンググループを立ち上げ、私はその座長を務めました。
最初の難題は、用語をどうするかということでした。
海外で用いられていた「Frailty(フレイリティ)」は日本語で“虚弱”などと訳されていましたが、虚弱という言葉はネガティブな印象を与えるのではないかと、使うのに抵抗を示す方たちもいました。そこでもっとニュートラルな感じにしたいと考え、「フレイル」という用語にしようと提案したのです。おかげさまでメディアなどでも取り上げていただき、今ではフレイルという言葉も少しずつ浸透してきました。
もちろん、言葉が広がるだけではダメです。フレイル対策の重要性が広く認識され、実践されなければ、健康寿命を延ばすというゴールにつながりません。そこで我々がいる国立長寿医療研究センター(以下、長寿研)ではさまざまな研究や活動を通じて、医師や専門家だけでなく、国民の皆さまに活用してもらえる情報を提供し始めています。
具体的には、まず基礎研究の領域では、フレイルになりやすいかどうかを判定する遺伝子の研究を進めています。また、最新のICT機材を用いて食事や睡眠の内容をモニタリングし、それを分析してフレイルの予測が可能かどうかも検討しています。
一方、病院ではロコモフレイル外来を設立し、フレイルやロコモ(ロコモティブシンドローム)※が不安な方に対して検査を実施したり、必要な人には治療を行ったりしています。
- ロコモティブシンドローム:骨、関節、筋肉などの運動器の障害のために移動機能に支障を来たした状態
男女別、このような人は要注意!早期対策を
AIの普及によって、いずれはさまざまな生活、身体、血液データなどを元に個別化された診療や指導ができる時代が来ると思います。遺伝子の結果から「何もしなくても元気でいられる人」や、「若いときからきちんとした生活習慣を送った方がいい人」がわかるかもしれません。
しかし、それができない今は、できるだけフレイルにならないよう、一人ひとりがしっかりと対策をとることが大事になってきます。
特に以下のようなリスクがある人は、早期から対策を始めたほうがいいでしょう。
まずは、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満といった生活習慣病を〝複数〟抱えている人や内臓肥満に他の生活習慣病が加わったメタボリックシンドロームの人です。こういう人は生活習慣が適切ではないケースが多いので、加齢による身体の機能が低下しやすいというリスクがあります。
次は、やせていて筋肉があまりない人です。先のメタボリックシンドロームは男性に多い傾向がありますが、こちらは若い女性に目立ちます。食事制限が過度になったり、誤った食習慣をしたりしていると、低栄養の問題が出てきます。その結果、更年期以降に骨や免疫など、さまざまな機能が低下しやすくなります。
心当たりがある人は「まだ大丈夫」と過信せず、対策をとっていただきたいです。
「フレイル対策」の5つのポイントとは
では、どんな対策をとればいいのか。私たちはフレイル対策として、次の5つのポイントを紹介しています。
- 適切な運動習慣
有酸素運動にレジスタンス運動(筋トレ)を加えた運動習慣は、高齢になってから始めるのは至難の業。若いころから習慣化することが大切です。歩行なら1日8000~9000歩、有酸素運動なら30分が目安。筋トレは腕立て伏せやスクワットなど何でもよく、階段を登るなど、すき間運動として取り入れてもOKです。
- バランスのよい食事
脂質、糖質、たんぱく質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂るのが基本。なかでも、たんぱく質とビタミンDは意識して摂りましょう。食事を毎回チェックするのは難しいので、スマホのアプリなどの活用をしてもいいでしょう。
- 社会交流・社会参加
人とのコミュニケーションもフレイル対策に役立ちます。人と会う機会がない・少ないという人は、意識して社会的な活動に参加されるのが望ましいです。リアルな人との付き合いが得意ではないという人は、オンラインなどで他者とコミュニケーションをとってもいいと思います。
- 病気の管理
高血圧や糖尿病など、生活習慣病などがある人は、かかりつけ医のもとでしっかり病気をコントロールすることが大事です。
- 口の健康
最近は8020運動の成果もあって、日本人の多くが80歳でも歯が20本以上残っています。食べものをしっかり噛み、しっかり話すには口の健康が大事です。毎日きちんと歯磨きをすることに加え、定期的に歯科検診を受けるようにしましょう。
<参考> 長寿研も高齢者の身体活動時間の低下や交流機会の減少を改善し、オンライン(インターネット)を活用して運動や健康づくりに取り組める介護予防アプリを用意しています。

荒井先生が実践している「フレイル対策」
もちろん私もフレイル対策に取り組んでいます。
運動でいえば、自宅にエアロバイクがあるのでそれを30分くらい漕いだり、腕立て伏せやスクワットをしたりしています。時間があるときは、ジムに行ってパーソナルトレーナーの指導の元、有酸素運動と筋トレをしています。
食事は……今は単身赴任なので、バランスのよい食事を摂るのは難しいなぁと実感しています。それでも昼間は長寿研の社食で野菜の多い献立を選ぶようにし、夜は自炊を心がけています。最近よく作るのは、ひとり鍋ですね。野菜やきのこはもちろん、肉や豆腐を入れて、たんぱく質が足りるようにしています。鍋は体も温まりますし、簡単にできるのでおすすめです。
社会交流は職業柄、こうして人と会って話をするということが、一番のフレイル対策なのかなと思っています。
「もしかして」と思ったときの通いの場と相談先
社会交流といえば、国はフレイル対策のための施策として、地域の人がお互いに交流できる「通いの場」を作り始めています。
この通いの場の多くは、自治体のサポートを受けて自主グループが運営しています。インターネットなどで検索してみるといいでしょう。また、地域の福祉情報が集まっている地域包括支援センターなどでも情報を入手することができます。
通いの場がない、知らない場に行くのはハードルが高い、リアルな交流は苦手……という方は、長寿研が作成した「オンライン通いの場」はいかがでしょう。つながった人たちとの交流だけでなく、健康管理もできるので便利です。
フレイルが気になる方、ご家族の相談先は、かかりつけ医がいればその先生に聞いてみるのが一番です。ほかには老年科専門医やフレイルサポート医※、サルコペニア・フレイル指導士などがいますので、専門的な視点でアドバイスをしてくれると思います。
自分自身でフレイルかどうかチェックをしたい方は、WHO(世界保健機関)が出しているICOPEを長寿研が日本語訳をしているので、それを活用するのもいいでしょう。
- 東京都・長野県のみ
「フレイル対策」に漢方薬が役立つことも
ここまでフレイルへの対策について解説してきましたが、先に挙げたような生活習慣の改善をはかっても変化が見られない症状もあるかもしれません。そういう場合に期待できるのが、漢方薬です。疲れやすい体質を改善する、睡眠の質を高める、食欲を上げるといった症状は、漢方薬で改善できることもあります。
ありがたいことに、今の日本の医療制度ではどの医師も漢方薬を処方することが可能です。ただ、その方の体質や症状などに応じて漢方薬が処方されることが望ましいので、できれば漢方に詳しい医師に相談したほうがいいと思います。
荒井先生から読者にメッセージ
可逆性があって対策が可能なフレイルですが、状態が悪くなればなるほど元の状態に戻りにくくなり、〝ポイント・オブ・ノー・リターン〟という、あるレベルまでいくと元には戻ることができなそうなこともわかってきています。
実際問題として、高齢になるほどこれまでの生活習慣を変えるのは難しいですし、状態が悪くなってからの努力と、それほど悪くなっていないときの努力を比べたら、圧倒的に後者のほうがラクです。
ですので、対策を始めるのは早ければ早いほどいい。若いうちから将来のことを考えた生活習慣を身に付ける、〝ライフコースアプローチ〟は大事です。今のフレイル検診は後期高齢者が対象ですが、75歳から始めるのでは遅すぎると私は思っています。
日本の平均寿命は男性が約81歳、女性が約87歳です。読者の方々が高齢になるころにはもっと平均寿命が延びているでしょう。40代、50代はそういう意味では〝人生の折り返し地点〟でしかありません。
残りの人生をどうやって健やかに過ごすのか、今からの生活習慣にかかっていることをぜひ心に留めて、フレイル対策をしていただけたらと思います。
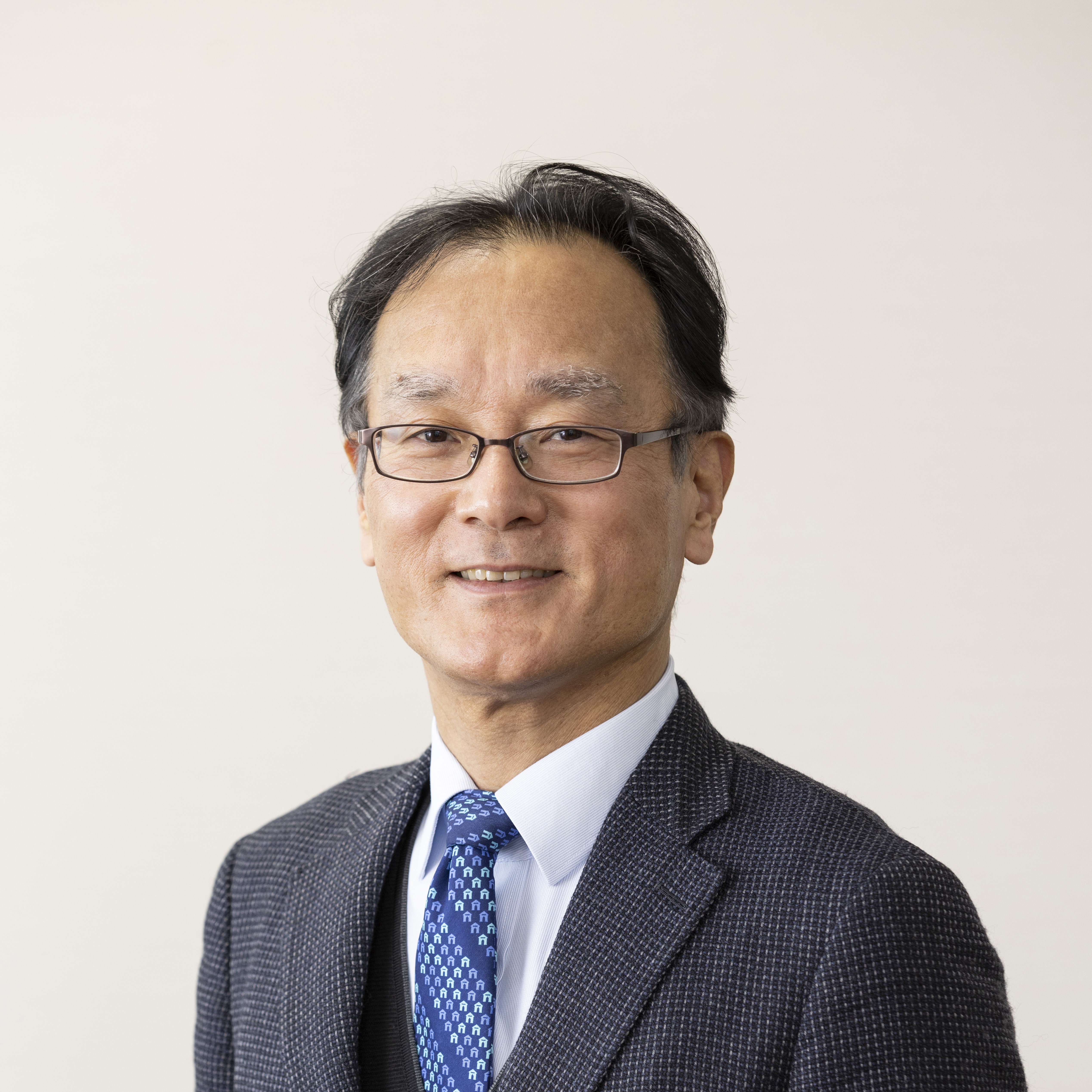
医師プロフィール
国立長寿医療研究センター 理事長
荒井 秀典先生
1984年京都大学医学部卒業、1991年京都大学大学院博士課程修了。医学博士。
2009年京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻教授を経て、2015年国立研究開発法人国立長寿医療研究センター副院長、2018年同病院長、2019年より同理事長(現職)。
日本サルコペニア・フレイル学会代表理事、日本老年医学会理事、 日本老年学会理事長、 日本学術会議第25、26期会員(第2部、臨床医学委員会)等を歴任。
専門は老年医学一般、フレイル、サルコペニア、脂質代謝異常。
関連コンテンツ
Keywords
- フレイル
- 早期対策
- 漢方
- フレイル対策
- 疲れやすい