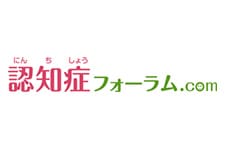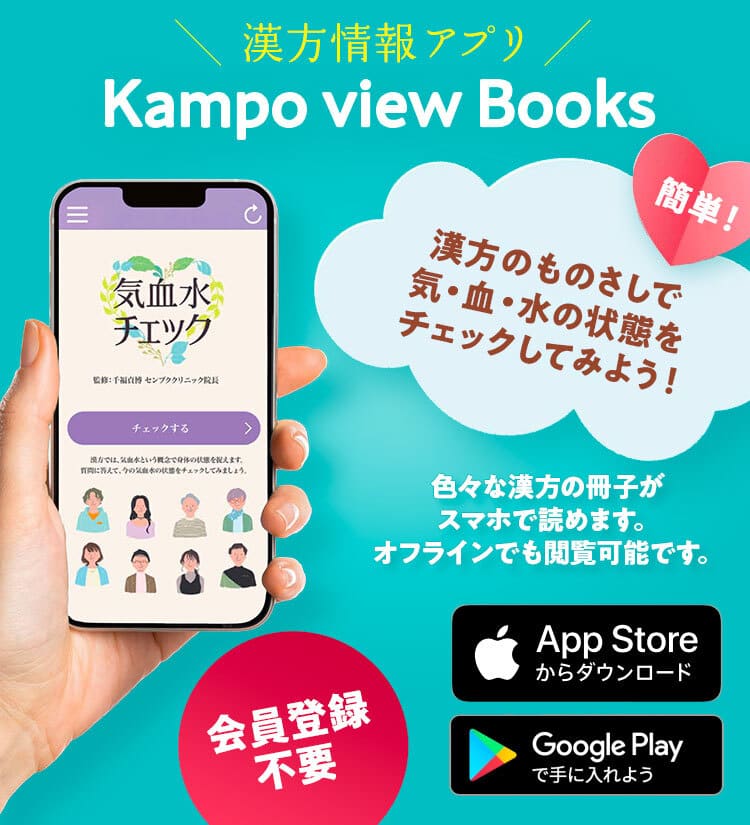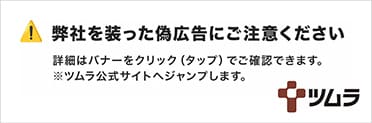「プレハビリテーション」という考え方
病気やコロナウイルス感染症で自宅療養したあとや、入院して治療を受け退院したあとに「体力がずいぶん落ちた」と感じる人が多いと思います。
じつは近年、入院などでカラダを動かさない状態が続くと体力が落ちることを「廃用症候群」と呼んで、問題視されるようになってきています。廃用症候群はとくに高齢者の問題になりますが、若い人でも療養が続けば当然のことながら体力が落ちるので、注意が必要です。
そんななか、手術に備えて体力アップを図るトレーニングなどを行う「プレハビリテーション」という考え方が注目されています。術後に行うリハビリテーションの逆の考え方で、ハーバード大の医師が名付けたといわれています。
入院によって体力が落ちることを前提に、事前に体力を付けておこう。
こうした考え方は、手術だけでなく、抗がん剤治療などでも徐々に浸透しているようです。
1週間寝たままだと筋肉が1割ほど失われる
プレハビリテーションには決まったやり方があるわけではないようですが、入院前にする運動として筋力をアップさせるためのスクワットや、有酸素運動のウォーキングなどが推奨されています。
同時に、筋肉の材料となるたんぱく質や、筋肉が作られるのをサポートするビタミンDなどを摂ることもすすめられています。
また、始める時期ですが、日ごろの運動の程度や体力の有無にもよりけりですが、最低でも1週間以上前から開始したほうがいいとのことです。
ところで、なぜ入院中や療養中に体力が落ちるのかというと、それは筋力が低下するからです。「廃用症候群」の研究では、安静な状態で寝たままだと、1週間で10~15%、1カ月ほどで半分ぐらい筋力が低下することがわかっています。
一度落ちた体力を取り戻すには3倍時間がかかる
療養や入院で一度落ちた体力を戻すのは、けっこうたいへんです。
海外の研究によると(高齢者の研究にはなりますが)、体力を取り戻すのに3倍以上の時間がかかるとされています。1日入院したら3日がんばらないと元に戻らないのです。
冒頭に紹介したプレハビリテーションは、手術や療養の日程があらかじめ決まっていれば行えますが、急に病気になったときはそうはいきません。
では、どうしたらいいかというと、まずは体力を落とさないために、術後や療養中も可能な範囲でカラダを動かすことが重要です。可能な範囲については病気や手術の内容にもよるので、主治医に相談した上で行うようにしましょう。
術後はプレハビリテーションのところでも紹介したような、筋肉を付ける運動と、筋肉の材料となる栄養素をしっかり摂り、体力アップを図ります。

病後の体力改善には漢方薬が有用なことも
病後の体力改善という意味では、漢方薬が有用となる場面も少なくありません。
実際、「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」や、「十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)」、「黄耆建中湯(おうぎけんちゅうとう)」、「人参養栄湯(にんじんようえいとう)」などが用いられています。
これらの漢方薬は「補剤」と呼ばれる種類で、その漢字が示している通り、胃腸の衰えを改善させることで「気(生命エネルギー)」など体内に不足しているものを補い、元気をもたらすことを目的にしています。
もちろん、日頃から体力が落ちてきたなと、不安に感じている人も服用することはできますので、気になる人は漢方に詳しい医師や薬剤師に相談してみるとよいでしょう。

参考
Oct 7 2022
医療ライター・山内
関連コンテンツ
Keywords
- COVID-19
- ウイルス
- エクササイズ
- 疲労
- 運動
- 養生