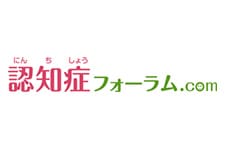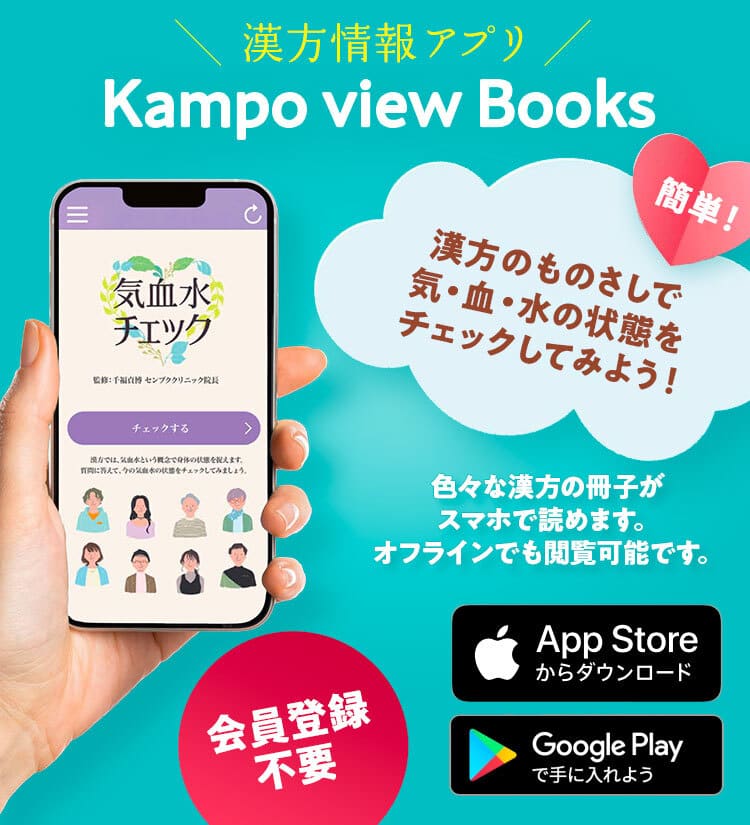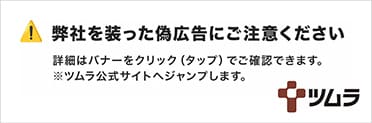「腎」の働きが衰えた高齢者に元気をつける
高齢者に用いられることが多い薬で、体力があまりなく、疲労や倦怠感が激しく、寒がりで特に手足や腰から下が冷え、夜間にトイレへ行くことが多いような人、のどが渇く人によく用いられます。漢方では、これらは「五臓」※の「腎」の働きが低下した「腎虚」による症状ととらえ、「腎」を元気にして改善をはかります。 頻尿・夜間頻尿、排尿困難、残尿感、軽い尿漏れ、腰痛、しびれ、かすみ目など、老化にともなう症状に用いられます。
- 五臓:西洋医学とは異なる臓のとらえ方で、肝・心・脾・肺・腎の働き
冷えにともなう痛みを体を温めて取る
冷えにともなう痛みを取るのによく用いられる「附子剤」の一つでもあり、体を温めることで、中高年によくみられる足腰などの慢性的な痛みやしびれの改善をはかります。 高血圧にともなう症状(肩こり、頭重、耳鳴り)などにも使われています。
配合生薬
地黄(じおう) 、 山茱萸(さんしゅゆ) 、 山薬(さんやく) 、 沢瀉(たくしゃ) 、 茯苓(ぶくりょう) 、 牡丹皮(ぼたんぴ) 、 桂皮(けいひ) 、附子末(ぶしまつ)
出典:「NHKきょうの健康 漢方薬事典 改訂版」 (主婦と生活社)
無断転載・転用を固く禁じます。