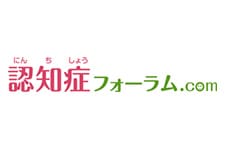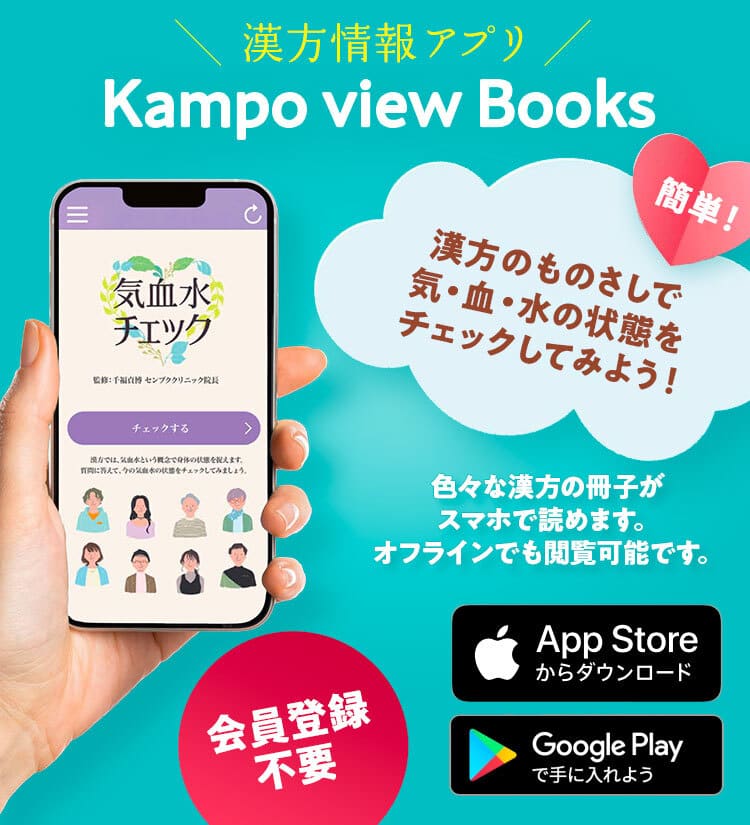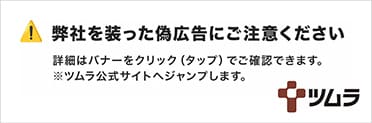疲労・衰弱している人の気力と体力を補う
全身が弱って、漢方でいう「気」も「血(けつ)」※も著しく不足している人に向く漢方薬です。不足を補う「補剤」の代表的なひとつです。
疲労倦怠感、貧血、皮膚の乾燥、食欲不振、寝汗、手足の冷えなどの不調があるときに処方されます。病後・手術後の体力低下をはじめ、産後の衰弱、貧血、冷え症の改善など、さまざまな目的で使われています。
-
「気・血・水」は、不調の原因を探るためのものさしです。漢方では、私たちの体は「気・血・水」の3つの要素が体内をうまく巡ることによって、健康が維持されていて、これらが不足したり、滞ったり、偏ったりしたときに、不調や病気、障害が起きてくると考えられています。
「気(き)」:目には見えない生命エネルギーのこと。「元気」の気、「気力」の気、「気合い」の気。「自律神経(体の機能を調整する神経)」の働きに近いとされています。
「血(けつ)」:全身を巡ってさまざまな組織に栄養を与えます。主に血液を指します。
全身状態をよくして闘病を助ける
最近では「十全大補湯」の、全身状態をよくして体力をつける効果を利用した応用も広がっています。例えばがん治療では、手術後の体力回復を助けるために活用されています。
配合生薬
黄耆(おうぎ)、 桂皮(けいひ)、 地黄(じおう)、 芍薬(しゃくやく)、 蒼朮(そうじゅつ)、 川芎(せんきゅう)、 当帰(とうき)、 人参(にんじん)、 茯苓(ぶくりょう)、 甘草(かんぞう)
出典:「NHKきょうの健康 漢方薬事典 改訂版」 (主婦と生活社)
無断転載・転用を固く禁じます。