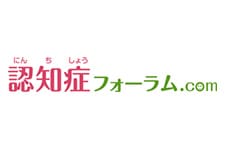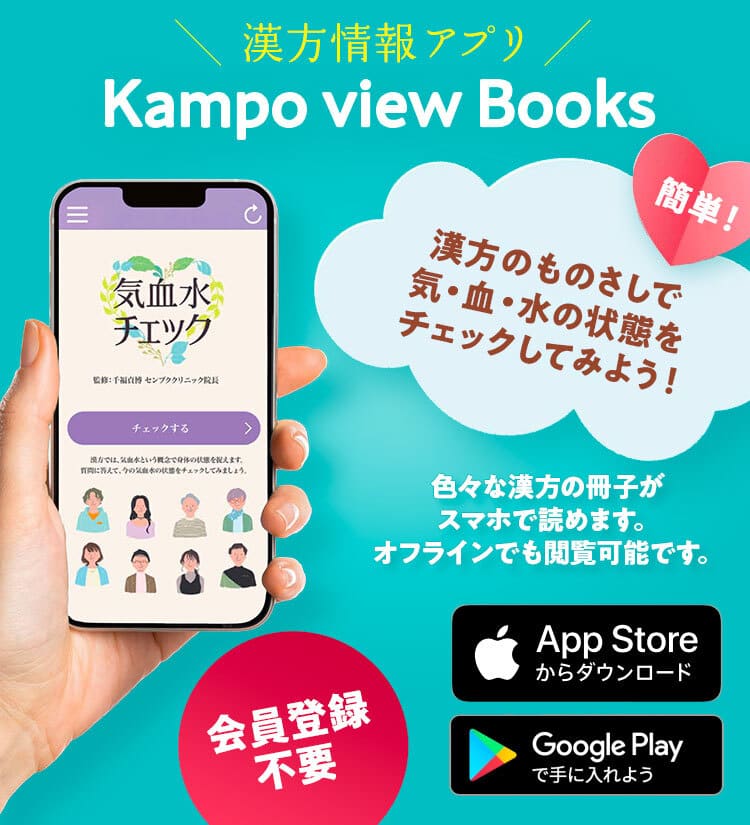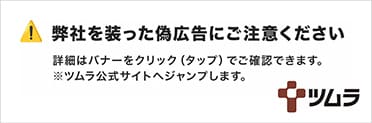「虚証(きょしょう)」のかぜの初期に使われ、高齢者にも向く薬
主にかぜの初期に用いられる漢方薬ですが「葛根湯(かっこんとう)」と違い、体力がなかったり、胃腸が弱かったり、あるいは日頃から疲れやすくかぜをひきやすいなど、病気を体の外へ追い出す力が弱い「虚証」の人や高齢者に向く薬です。
頭痛、寒気、発熱(主に微熱)、のぼせ、軽いうなじのこわばりや体の痛みなどの症状があり、皮膚が自然に汗ばむときに用いられます。
「虚証」の人は体温が上がらないで自然に汗をかき、熱があっても顔色が悪いことがあります。
「桂枝湯」をもとにさまざまな漢方薬が誕生
中国・漢代の『傷寒論(しょうかんろん)』という医学書の最初に出ている薬です。現在の漢方薬は、この「桂枝湯」をベースに、ほかの生薬を加減して応用範囲を広げているものが多くみられます。
配合生薬
桂皮(けいひ)、 芍薬(しゃくやく)、 大棗(たいそう)、 甘草(かんぞう)、 生姜(しょうきょう)
出典:「NHKきょうの健康 漢方薬事典 改訂版」 (主婦と生活社)
無断転載・転用を固く禁じます。