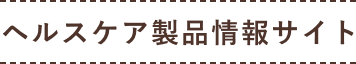2025.11.26
養生のすすめ
入浴
日本の「入浴剤」進化の物語
私たち日本人にとって、お風呂は単に身体の汚れを落とすだけでなく、一日の疲れをリセットし、心を解きほぐすための「大切な時間」と言えるでしょう。この日本独自の入浴文化を、さらに奥深く、彩り豊かに演出してくれるパートナーが「入浴剤」です。
今や、その日の気分や体調に合わせて選ぶのが当たり前となった入浴剤。しかし、その一包、一錠が、婦人薬から始まり、時代の変化と共に、驚くべき進化を遂げてきたことをご存知でしょうか。
今回は、入浴剤の知恵と革新の歴史を、紐解いていきます。
第1章:入浴剤の原点。自然の恵みを湯に溶かす「植物浴」の知恵
日本の入浴剤の歴史は古く、室町時代の『庭訓往来』(ていきんおうらい)に「五木八草湯(ごぼくはっそうとう)」という記録が残されています。これは、「五木」は桃・梅・柳・桑・槐・椿・杉などの樹木、「八草」は菖蒲・蓮・車前草・聾・猫:忍冬(樹木)・熊葛・繁緩などの草本で、いずれも日本の土地に生える植物です。これらを刻んで湯に入れて蒸気浴をするというものです。
これは単なる香りづけではなく、植物が持つ薬効成分を湯に溶け出させ、健康維持や病の予防に役立てようとした、まさに「薬湯」の原型です。
江戸時代に入ると、植物をお湯に入れて入浴するという知恵は庶民の間にも広がりを見せます。例えば「すいかずら(忍冬)」の葉を利用している銭湯の様子が「浮世風呂」にも記載があり、実際に葉や茎を湯に入れると、その抗菌・抗炎症作用から、あせもや湿疹に良いとされていました。また、桃の葉(桃湯)も同様にあせも対策として親しまれました。

そして、この植物浴の文化が、季節の行事として行われ、現代にも続くのが、冬至の「ゆず湯」と端午の節句の「菖蒲湯」です。 「ゆず湯」は、冬至(とうじ)を「湯治(とうじ)」にかけ、柚子(ゆず)を「融通(ゆうずう)が利く」にかける語呂合わせと共に、その強い香りで邪気を祓い、血の巡りを良くして風邪を防ぐという実利的な健康法でした。 「菖蒲湯」も同様に、菖蒲(しょうぶ)の独特の強い香りが邪気を祓うとされ、また「菖蒲」が「尚武(武事を尊ぶ)」に通じることから、男の子の健やかな成長を願う行事となりました。
このように、日本の入浴剤文化は、単なる嗜好品としてではなく、自然の力を借りて健康を維持する、季節の節目を祝うという、暮らしに根付いた「生活の知恵」として広がっていきました。
第2章:製品の誕生。明治の「くすり湯 浴剤中将湯」という奇跡
日本で初めて「商品」として販売されたのが、明治30年(1897年)、株式会社ツムラの前身である津村順天堂の「くすり湯 浴剤中将湯」です。
当時、津村順天堂は婦人薬として漢方薬「中将湯※」を製造販売していました。 これは冷えや婦人特有の悩みに応えるための煎じ薬です。その製造過程で出る生薬の残りカスを、ある社員が自宅に持ち帰り、盥(たらい)の湯船に入れ子供を入浴させたところ、いつまでも子供の体がポカポカと温かく、また、湿疹も改善したのです。
この偶然の発見が、創業者・津村重舎の耳に入り、製品化され販売されたのが「くすり湯 浴剤中将湯」です。「飲む」婦人薬が「浸かる」入浴剤へと生まれ変わった瞬間でした。残りカスを再利用した製品ということは今でいうエコ商品とも言えます。
この製品が発売されたのは、内風呂がある家がまだ少ない明治時代でした。多くの人々は「銭湯」に通うのが日常でした。したがって、この日本初の入浴剤は、「銭湯」向けに販売されたため、日常の銭湯を「特別な健康の場」に変えるアイテムとして、たちまち人気を博しました。
※1897年(明治30年)当時の製品を指しています。
第3章:大衆化への道。「バスクリン」の革新と色彩の魔法
「くすり湯 浴剤中将湯」は高い人気を得ましたが、一つの大きな課題がありました。生薬の力で非常に体が温まるため、「冬は最高だが、夏は入浴後に汗が引かない」という、嬉しい悲鳴ともいえる声が寄せられたのです。
そこで、季節を問わず誰もが楽しめる、新しい時代の入浴剤の開発が始まります。 津村順天堂は、京都大学の刈米(かりよね)教授ら専門家の力を借りました。そして、「温泉」の成分に着目します。
こうして、初めて温泉成分(無機塩類)を応用し、生薬とは異なるアプローチで体を温め、さらに色素と香料を加えた、まったく新しい製品が開発されました。 これが、昭和5年(1930年)に誕生した「芳香浴剤 バスクリン」です。

バスクリンは、色素には「ウラニン」を使用し、それまで無色透明が当たり前だったお湯が、オレンジ色の粉末を入れた途端、鮮やかな蛍光グリーンに変わるのです。この視覚的な「魔法」は、人々の心を鷲掴みにしたのではないでしょうか。
マーケティング戦略も、それまでの「薬湯」のイメージを覆す、極めてモダンなものでした。パッケージには、当時絶大な人気を誇った挿絵画家・高畠華宵(たかばたけ かしょう)が描く、優美でモダンな女性の入浴シーンを採用。さらに、「バスクリンの湯で顔を洗うとキレイになる」といった、美容への期待感をあおるイラストも描かれ、特に女性たちの強い憧れを誘いました。
ただし、価格は非常に高価でした。一缶(15人分)で80銭。現在の貨幣価値でいえば、およそ4,000円にもなります。高価なバスクリンを節約するため、一部の銭湯がお湯を換えないという社会問題にもなりました。
第4章:戦後復興と「内風呂」への劇的シフト
戦争の激化とともに「バスクリン」も製造中止を余儀なくされます。しかし、戦後の混乱期を経て、昭和25年(1950年)にガラス瓶にて販売を再開します。そして、日本の入浴文化における最大の転換点が訪れます。 昭和30年代(1955年〜)、高度経済成長と共に「公団住宅(団地)」が次々と建設され、「内風呂(家庭風呂)」が急速に普及し始めたのです。
この社会構造の変化を捉え、入浴剤の販売は「公(銭湯での共有)」から「個(家庭での占有)」へと大きくシフトします。毎日、自宅の湯船に、自分や家族のためだけに入浴剤を入れる。丁度このころからTVも多くの家庭で持つようになり「遠くの温泉より、我が家で温泉気分」というキャッチフレーズのTVCMも放送されるようになり、バスクリンは入浴剤の代名詞となっていきました。
家庭風呂が当たり前になると、消費者のニーズは「一家に一つ」から「一人ひとり」へと、さらに多様化し、そのニーズに応え、生薬の良さを追求した商品や、温泉からヒントをえた商品など、入浴剤の技術革新が加速します。
第5章:現代へ。健康を支えるパートナーとしての深化
そして入浴剤は、「温まる」「疲労回復」「香りや色を楽しむ」というものから、その日の疲れ、具体的な悩み(冷え、肩こり、乾燥など)に寄り添い、家庭での「健康入浴を演出する」重要なアイテムへとなっています。
明治時代、一人の社員の「もったいない」という気づきから生まれた日本の入浴剤。 それは、植物の知恵という原点があり、時代のニーズと科学の力で進化を遂げ、一つの日本人の入浴文化を築いたともいえるでしょう。 今夜はぜひ、その一包に溶け込んだ100年以上にわたる先人たちの知恵と革新に思いを馳せながら、ゆっくりと湯船に浸かってみてはいかがでしょうか。
執筆・監修
日本薬科大学 スポーツ薬学コース
特任教授 石川泰弘(いしかわやすひろ)
博士(スポーツ健康科学)
温泉入浴指導員(厚生労働省規定資格)
睡眠改善インストラクター(日本睡眠改善協議会認定資格)
「お風呂教授」として T V や雑誌をはじめとする多くのメディア活躍。
多くの日本代表チームやトップアスリートに対して入浴や睡眠を活用したリカバリーに関する講演なども行っている。