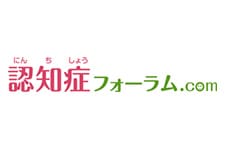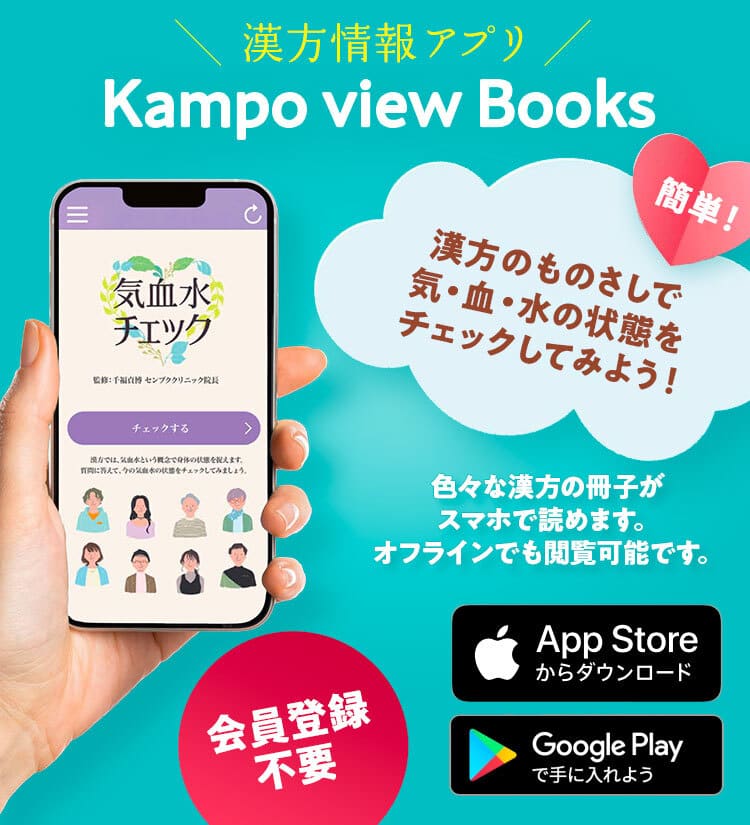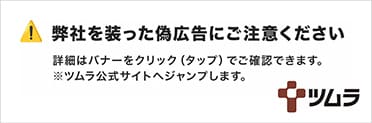江戸時代に華岡青洲によってつくられた漢方薬
「十味敗毒湯」は、中国の明の時代の医学書『万病回春(まんびょうかいしゅん)』に載っている「荊防敗毒散(ケイボウハイドクサン)」という処方をもとに、江戸時代の外科医、華岡青洲によって日本でつくられた漢方薬です。10種類の生薬で毒素を取り除くということから「十味敗毒湯」と名づけられました。化膿を抑え、皮膚の腫れや赤み、かゆみを取る薬です。
化膿しているおできや、化膿を繰り返すにきび、皮膚炎、湿疹、じんましん、水虫などの改善に使われます。特に、分泌物が少ない場合に多く用いられます。 中程度の体力で、薄墨色の顔色をしたような、比較的神経質な人に向く薬といわれます。
配合生薬
桔梗(ききょう) 、 柴胡(さいこ) 、 川芎(せんきゅう) 、 茯苓(ぶくりょう) 、 防風(ぼうふう) 、 甘草(かんぞう) 、 荊芥(けいがい) 、 生姜(しょうきょう) 、 樸樕(ぼくそく) 、 独活(どくかつ)
出典:「NHKきょうの健康 漢方薬事典 改訂版」 (主婦と生活社)
無断転載・転用を固く禁じます。