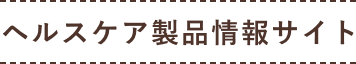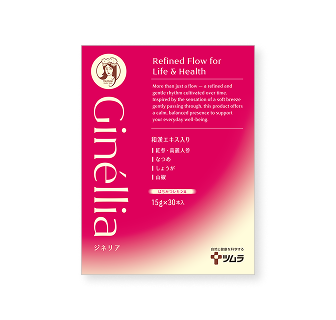2025.08.05
漢方ブログ
おなかのハリを解消するには? 日常に潜む原因と今すぐできるセルフケア
「おなかが張って苦しい」「ガスがたまって不快」そのような経験はありませんか? 日常的に起こるおなかのハリには、食生活やストレス、腸の冷えなど、さまざまな原因が関係しています。ここでは、おなかのハリの主な原因とともに、今日から取り入れられるセルフケア方法をご紹介。漢方の視点も交えて、無理なく快適に過ごすヒントをお届けします。
おなかのハリとは

おなかのハリは、主に腸にガスや内容物がたまり、腹部に膨らみや圧迫感、不快感のある状態を指します。「腹部膨満感」とも呼ばれ、食後や便通の乱れ、生理前後など、さまざまな場面で感じやすい症状です。「おなかがパンパン」「苦しい」など、人によって感じ方や表現は異なりますが、誰にでも起こり得る身近な不調の1つといえるでしょう。軽い一時的な張りであればあまり心配はいりませんが、頻繁に起こる・慢性的に続く場合は、生活習慣を見直すことが重要です。
おなかが張るメカニズム
食事や飲み物を摂る際には、知らず知らずのうちに空気を一緒に飲み込んでいることがあり、それが原因で膨満感が生じる場合があります。また、腸内細菌が食物を分解する過程でもガスは自然に発生します。通常、こうしたガスは自然に排出されますが、腸の動きが鈍り、腸内環境が乱れると、体内に留まりやすくなり、おなかのハリや膨満感を引き起こします。
おなかのハリ解消のカギとなる「脾」と「気」の関係
漢方では、食べ物の消化吸収をつかさどる「脾(ひ)」と、全身を巡るエネルギー「気(き)」のバランスが乱れると、腸の動きが鈍くなると考えます。胃腸機能が弱まり、消化吸収がうまく行われないと腸を動かすエネルギーである「気」が十分に生産されなくなります。この状態を漢方では「脾虚」と呼びます。「脾虚」の状態が続くと、腸の動きが鈍くなり、ガスや便が腸にたまるため、張りなどの不快な症状が現れます。「脾」の機能を高め、「気」の巡りを整えることが、おなかのハリを解消するカギとなります。
おなかのハリを引き起こす「脾」と「気」のバランスを崩す原因とは?
漢方では、おなかのハリの背景には「脾」と「気」のバランスの乱れがあるとされています。ここでは、それらの働きを弱める主な原因について解説します。
腸内環境の乱れ
食物繊維の不足や高脂肪の食事が続くなど、食生活が乱れると腸内の悪玉菌が増え、ガスを発生させるなど腸内環境が乱れます。すると腸の消化吸収がうまく機能しなくなり、「脾虚」の状態を引き起こし、おなかのハリにつながると考えられています。
食べ過ぎ・飲み過ぎ
「脾」は適量の食事を好む臓腑とされ、暴飲暴食はその働きを弱めると考えられています。過度の飲食は「脾」に負担をかけ、消化機能を低下させます。すると、腸を動かす「気」の巡りが滞り、腸の動きが鈍ってガスがたまりやすくなります。とくに脂っこいものや甘いものの摂り過ぎには要注意。「脾」に大きな負担をかけ、慢性的な膨満感を招きます。
おなかの冷え
「脾」は冷えに弱いとされ、冷たい飲食物の摂りすぎや冷房の効いた環境で長時間過ごすことは「脾虚」の原因になると考えられています。「脾」の働きが弱まると、腸の活動が低下し、ガスや便の排出が滞って膨満感や便秘につながります。こうした冷えによるおなかのハリを防ぐためにも、おなかを温めて「脾」の働きを守ることが大切です。
ストレスによる自律神経の乱れ
漢方では、ストレスは「気」の巡りに影響すると考えられています。ストレスが続くと「気滞」の状態になり、腸の動きが鈍りやすくなります。また、「脾」の働きも抑えられ、「脾虚」によって腸を動かす力そのものが不足しがちです。心と体は密接につながっているため、精神的な緊張が、おなかのハリや不快感を引き起こす原因になることもあります。
漢方で考えるおなかのハリ対処法

漢方では、「脾」の働きと「気」の巡りを整えることが、おなかのハリの解消につながると考えられています。「脾」の働きを補い、「気」の巡りを整える生薬を取り入れて、体の内側から整えていくことがポイントとなります。
腸の動きが悪くなって起こるおなかのハリには「大建中湯 だいけんちゅうとう」
食生活の乱れやおなかの冷え、ストレスなどによって腸の動きが鈍ると、ガスの排出が滞り、おなかのハリや不快感につながることがあります。そのようなときに効果的とされているのが、漢方薬の「大建中湯」です。乾姜・山椒・人参といった生薬が配合されており、腸の動きを正常化することで、ガスや便の排泄を促し、おなかのハリを改善する効果が期待できる漢方薬です。また、温度感覚センサーにアプローチし、腸を温め、リズムを整えることで、腸の動きをサポートします。おなかのハリが続くとき、体の内側から整える選択肢として、取り入れてみてはいかがでしょうか。
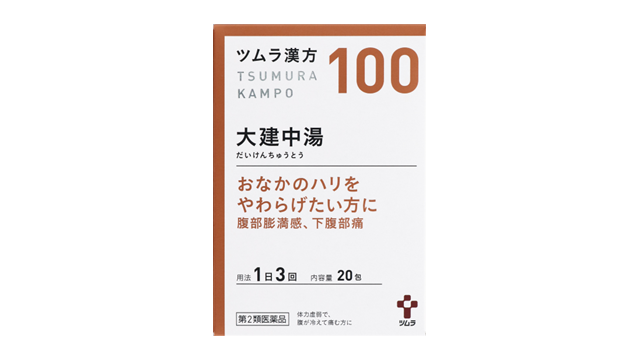
【効能・効果】
体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症:下腹部痛、腹部膨満感
自身のおなかのハリについて詳しく知りたい方はこちら
大建中湯が買える店舗を検索したい方はこちら
おなかのハリを改善するためのセルフケア方法
食べ過ぎ・早食いを控える
早食いや食べ過ぎは、「脾」に負担をかけて消化力を弱め、腸の「気」の巡りを乱す原因になります。よく噛んでゆっくり食べることが大切です。満腹になるまで食べず、腹八分目を意識しましょう。
腸内環境を整える食生活を心がける
ヨーグルトや味噌などの発酵食品や、野菜、果物、豆類といった食物繊維の豊富な食品を適度に摂ることは、腸内環境を整えるのに効果的です。また、「脾」をいたわるためには、食材の温度も大切な要素になります。冷たい飲食物は控えて、体を温めるものを摂るよう心がけましょう。
こまめに水分を摂取する
腸の潤いを保つためには、こまめな水分摂取を行うことが大切です。水分不足になると便が硬くなり、腸の動きが停滞しやすくなります。1日当たり1.2リットルを目安として、意識的に水分を摂るようにしましょう。冷えた飲み物は腸に負担をかけるため、常温の水や白湯がおすすめです。
湯船に浸かっておなかを温める
おなかを外から温めるには、入浴が効果的です。38~40℃程度のぬるめのお湯に15~20分ほど、ゆっくりと浸かりましょう。腸の動きが促され、ガスや便の排泄が整いやすくなります。心身の緊張を緩めてリラックスすることで、ストレス解消にも役立ちます。
軽めの運動を生活に取り入れる
軽めの運動は、気の巡りを良くし、腸の動きを活性化する効果があります。毎日10分でもよいので、無理なく続けることが大切です。運動不足が気になる方は、日々の生活にウォーキングやストレッチなどを意識して取り入れてみましょう。
おなかのハリが長く続く場合は、医療機関への受診を
慢性的なおなかのハリの背後には、病気が潜んでいることもあります。不快な症状が続く場合は、早めに受診して医師の診断を受けることが大切です。
おなかのハリを改善して、すっきり快適な毎日へ

漢方では、「脾」を整えて働きをよくすることや「気」の巡りを整えることで、腸の動きが良くなり、おなかのハリの根本的な改善につながると考えられています。「脾」の働きが弱まり、「気」の巡りが乱れる原因は、食生活や冷え、ストレスなど日常の中に隠れていることが多々あります。生活習慣の見直しとともに、体質に合った漢方ケアを取り入れて、すっきり快適な毎日を手に入れましょう。