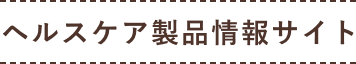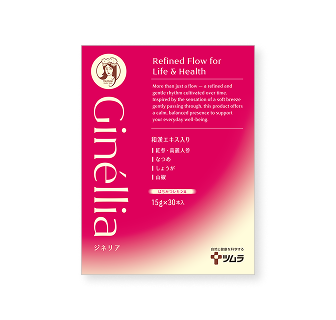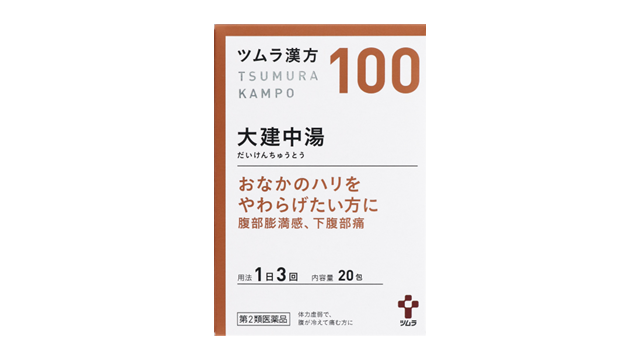2025.09.05
漢方ブログ
おなかのハリは"冷え"から?内側から整える対策法
おなかにハリや圧迫感がある……そんなお悩みの背景に「冷え」が関係していることをご存じですか? とくに、手足は温かいのにおなか周りだけが冷たい場合は、体の深部が冷えている可能性があります。このような冷えは気づきにくく、腸の働きを妨げて、おなかの不調を引き起こすことも。ここでは、冷えが原因となるおなかのハリについて、その仕組みと改善法をわかりやすく解説します。
冷えておなかが張る……それっておなかの冷えが原因かも?
手足は温かいのにおなかだけが冷たい、便秘や下痢を繰り返す、疲れやすいといった症状がある場合、体の内側が冷えている可能性があります。自覚しにくい冷えだからこそ、体からのサインを見逃さないことが重要です。おなかの冷えをそのままにしておくと、さまざまな不調を招くおそれがあるため、日頃から意識して対策していきましょう。
おなかの冷えがもたらす体への影響
おなかの冷えは、漢方でいう「脾(ひ)」の働きを弱め、「気」の巡りを滞らせる原因になります。「脾」は、食べたものから「気」や「血」を生み出す重要な役割を担う部分です。冷えによって「脾」が弱まると、腸の動きが鈍り、便秘や下痢、ガスだまりなどの不調が起こりやすくなります。さらに、「気」の巡りが悪くなると、疲れやすさや肩こり、肌荒れなど、全身に影響が広がることもあり、「たかが冷え」と軽く考えるのは禁物です。
おなかの冷えのサイン
みぞおちのあたりを手のひらでそっと触れてみて、ひんやりと感じるようであれば、おなかが冷えている可能性があります。朝起きたばかりのタイミングは、脇とおなかの温度がほぼ同じなのが自然な状態です。脇と比べておなかが冷たいと感じたら、冷え対策を意識しましょう。
冷えによっておなかが張るのはなぜ?

おなかが冷えると、腸の働きが鈍り、張りや違和感といった不調を引き起こしやすくなります。ここでは、冷えが腸にどのような影響を及ぼすのかを見ていきましょう。
血行不良による腸の働きの低下
おなかが冷えると血流が悪くなり、腸に必要な栄養や酸素が届きにくくなります。その結果、腸の動きが鈍くなり、腸内環境が乱れがちに。ガスの排出がうまくいかなくなり、張りや不快感が生じる原因となります。
自律神経の乱れによる腸内環境の悪化
冷えが続くと自律神経のバランスが崩れ、腸のリズムにも影響を及ぼします。腸内環境が乱れることで、消化や排出のタイミングが乱れ、おなかにガスがたまりやすくなるのです。これにより、慢性的なおなかのハリや不快感を抱くことがあります。
筋肉の緊張による腸のこわばり
体が冷えると腹部の筋肉が緊張し、腸のしなやかな動きが妨げられます。腸がこわばることで、ガスの移動や排出がスムーズに行われず、おなかのハリやゴロゴロとした違和感を引き起こすことがあります。
知らずにやっている?おなかを冷やす生活習慣

毎日のちょっとした行動が、知らないうちにおなかを冷やしてしまっていることも。漢方では、おなかの冷えは「脾」の働きを弱め、「気」の巡りを滞らせる原因になるとされています。次のような生活習慣は、知らず知らずのうちに体を冷やし、「脾」や「気」のバランスを乱しているかもしれません。腸の動きを妨げないためにも、普段の生活を見直してみましょう。
冷たい飲食物を取りすぎている
冷たい飲み物や生野菜を多く取ると、「脾」の働きが弱まりやすくなります。漢方では、「脾」は「喜温悪寒(きおんおかん)(温かい環境を好み、冷えを嫌う)」とされるため、内側から体を冷やすと消化機能の低下を招きます。腸の動きも鈍くなり、ガスがたまっておなかが張りやすくなります。
入浴はシャワーだけで済ませる
最近は「お風呂離れ」ともいわれ、とくに若い世代を中心に湯船につからずシャワーだけで済ませる人が増えています。しかし、シャワーでは体が芯まで温まらず、内側は冷えたままの状態に。「気」の巡りが滞りやすくなり、腸の働きにも影響を及ぼします。忙しい日でも、できるだけ湯船につかって体の芯まで温める習慣をつけたいところです。
デスクワーク中心で運動不足
現代人の多くは、長時間のデスクワークで同じ姿勢を取り続ける生活を送っています。運動不足は「気」の巡りを妨げる原因の1つです。「気」の流れが悪くなると、体が冷えやすく、腸の働きも低下しやすくなります。その結果、おなかのハリが起こりやすくなるのです。
薄着や締め付けの強い服装
季節に合わない薄着や、下腹部を締め付けるような服装は、「気」の巡りを妨げ、おなかを冷やす原因になります。とくにウエスト周りが冷えると腸の働きに影響し、おなかのハリや不快感を引き起こすことも。冷えを防ぐには、服装選びも大切です。
冷えによるおなかのハリを改善するには

おなかのハリが冷えからきている場合は、体を内側から温める習慣を取り入れることが大切です。日常生活の中で無理なく取り入れられる冷え対策を紹介します。
温かい食べ物を積極的に取る
温かい食事を取り入れて、内側から消化器を温めることは、「脾」の働きを助け、腸を動かすために重要です。温かいスープや煮込み料理、温野菜、根菜類などを取り入れることで、おなかからじんわり温まりやすくなります。できるだけ冷たい飲み物、とくに氷入りのものは避けて、温かい飲み物や常温の飲み物を取るように心がけましょう。
湯船につかって体を芯まで温める
湯船にゆっくりつかることで、「気」の巡りが整い、「脾」の働きも活発になります。しかし、冷えた体を早く温めようと、42℃以上の熱いお湯につかるのはNG。体が芯まで温まらない可能性があります。38〜40℃程度のぬるめの温度で10分以上、できれば30分程度を目安に入浴するのがおすすめです。副交感神経が優位になり、腸の動きにもよい影響を与え、おなかのハリや不快感の軽減にもつながります。
腹巻きやカイロで腹部を温める
腹巻きやカイロなどでおなかを外側から温めることは、冷え対策として効果的です。腹部を温めることで「脾」の機能をサポートし、「気」の巡りを整える助けにもなります。冷房の効いた室内で長時間過ごすときも、おなか周りを冷やさないよう意識しましょう。
適度な運動を習慣化する
ウォーキングや軽いストレッチなどの有酸素運動は、体内に熱を生み出し、冷えの予防に役立ちます。体を動かすことで「気」の巡りが整い、腸の働きが活性化され、たまったガスの排出も促されます。ただし、くれぐれも無理は禁物です。1駅分歩いたり、ストレッチや軽い体操を取り入れたりなど、できることから無理なく始めてみてください。
締め付けの少ない服装を選ぶ
きつめのボトムスやウエストを強く締め付けるような服装は、「気」の流れを妨げて体を冷やし、「脾」に負担をかけるおそれがあります。なるべく締め付けの少ない服装で、血流を妨げないようにしましょう。おなかをやさしく包むようなアイテムを選ぶのがおすすめです。
漢方を取り入れて、内側から温める
冷えによるおなかのハリや下腹部の痛みが気になる方は、日々のケアに漢方薬を取り入れるのも方法の1つです。
「大建中湯(だいけんちゅうとう)」は、冷えが原因でおなかが張ってつらい方におすすめの漢方薬です。この漢方薬は、単におなかを温めるだけでなく、腸のぜん動運動を改善し、つらいおなかのハリを根本から改善することを目指します。
大建中湯が持つ独自の働きの一つが、腸の温度感覚センサーへのアプローチです。冷えた腸を内側からじんわりと温め、血流を促進します。その結果、滞っていた腸の動きが活発になり、ガスや便の排出が促されることで、おなかのハリをはじめとした不快な症状の改善が期待できます。
毎日のケアとして大建中湯を続けることで、冷えに負けない、すっきりとした健やかなおなかを目指せるでしょう。
【効能・効果】
体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症:下腹部痛、腹部膨満感
大建中湯のブランドサイトはこちら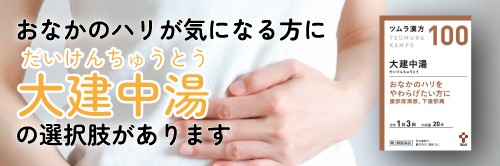
大建中湯が買えるお店を知りたい方はこちら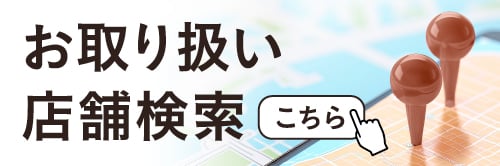
おなかの冷えに気づいたら早めの対策を
おなかのハリや不快感は、冷えが原因になっていることもあります。まずは生活習慣を見直し、温かい食事や入浴、漢方など、体を内側から温めるケアを取り入れてみましょう。毎日の小さな積み重ねが、すっきりとしたおなかを取り戻す一歩になります。