漢方の歴史


漢方は
日本独自の医学です
漢方は、治療に対する人間のからだの反応を土台に体系化した医学といえます。古代中国に発するこの経験医学が日本に導入されたのは5~6世紀頃。日本の風土・気候や日本人の体質にあわせて独自の発展を遂げ、わが国の伝統医学となりました。17世紀頃、特に大きく発展して体系化され、現在へと継承されています。
漢方という名称の由来は、日本へ伝来した西洋医学である「蘭方」と区別するためにつけられたものであり、もちろん、中国の伝統的な医学である「中医学」とも異なります。まさに漢方は、日本独自の医学なのです。
-
593〜 飛鳥時代
詳しく見る中国伝統医学伝来
中国から医療制度や医学を積極的に導入
5、6世紀頃に中国医学が仏教など他の文化とともに朝鮮半島経由で伝来し、7世紀には遣隋使、遣唐使が派遣され中国から医療制度や医学が直接導入されるようになります。
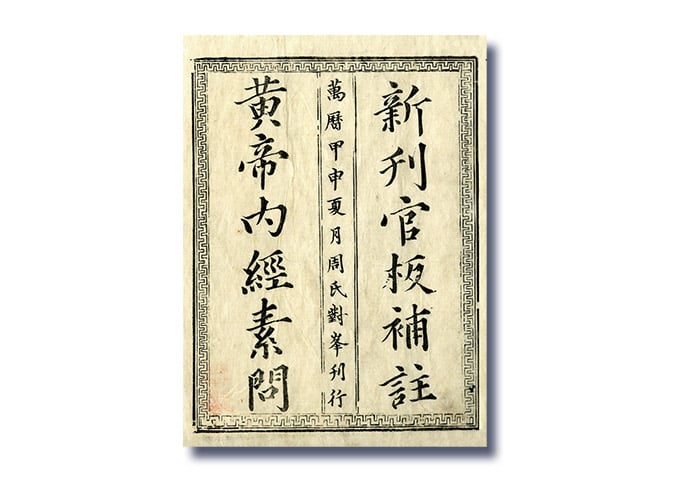
中国三大古典
黄帝内経
春秋戦国時代以来の医学論文を編纂した医学書。前漢末から後漢初期に成立。「素問」「霊枢」という二つの書から構成され、「素問」は生理・病理などの基礎医学が、「霊枢」は鍼灸治療法などの臨床医学が記されています。
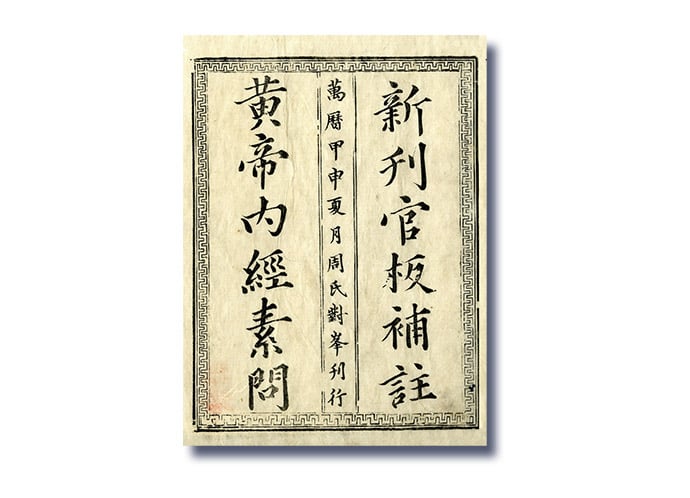
神農本草経
365種類の生薬を解説した中国最古の薬物学書。1、2世紀に成立。生薬の薬効によって上薬(不老長寿)・中薬(健康増進)・下薬(治療薬)の3種類に分類し、生薬の相互作用なども解説されています。
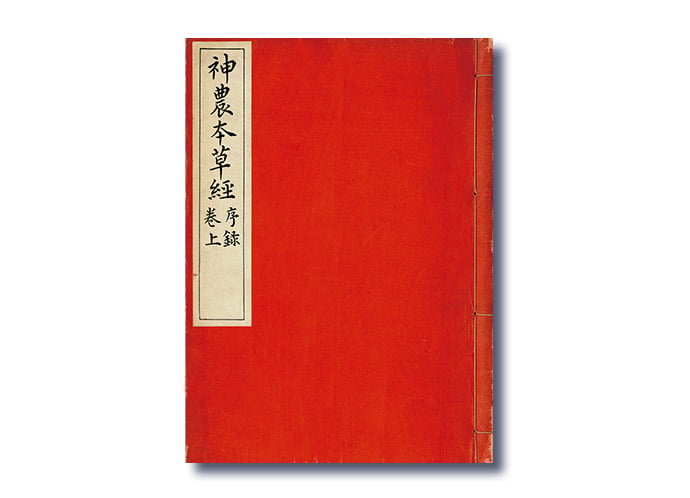
傷寒雑病論
約1800年前に張仲景がまとめた処方集です。「傷寒論」「金匱要略」の二つの書に分かれて現代に伝えられています。「傷寒論」は急性熱性疾患が、「金匱要略」は慢性疾患が記され、さまざまな病態への対応が記された実践的な薬物治療学書です。
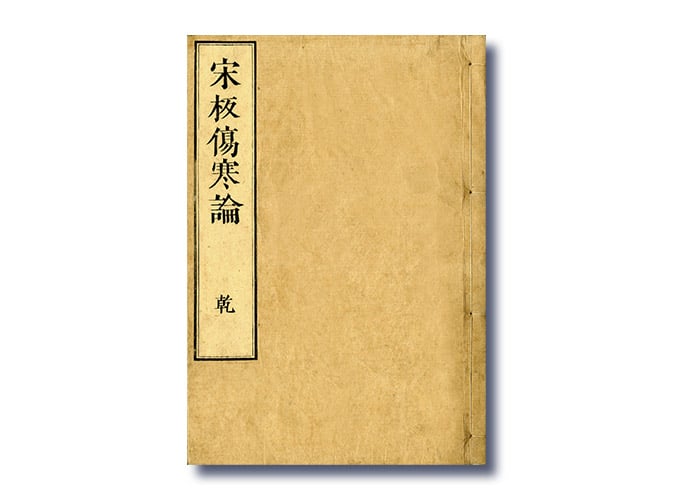
参考画像:【黄帝内経】【黄帝内経】【傷寒雑病論】ツムラ漢方記念館 所蔵
-
794〜 平安時代
詳しく見る中国伝統医学の模倣
日本の独自性を追求、わが国最古の医学書が日本人により編纂された
平安時代の日本は、まだ中国伝統医学を模倣していた時代です。984年に丹波康頼(たんばのやすより)が全30巻の日本最古の医学書「医心方」を編纂しています。中国の唐以前の古医書、百数十種からおよそ4700回もの引用で構成されたものです。丹波康頼は宮廷医で、この頃は貴族など、高貴な人だけが医療を施された時代でした。

丹波康頼(たんばのやすより) (912~995)
康頼は中国後漢の霊帝の子孫で、日本に帰化した阿智王より数えて八世の孫とされ、針博士・医博士となり、丹波宿禰の姓を賜り、宮廷医丹波家の祖となった。

参考画像:【丹波康頼】財)武田科学振興財団 杏雨書屋 所蔵
-
1185〜 鎌倉時代
詳しく見る医療の対象が一般民衆に拡大
鎌倉時代になると、医療の担い手が宮廷医から栄西(ようさい)のような僧医になり、医療の対象が一般民衆にまで拡大します。国内で編纂された医学書の中には、平易な仮名交じり文で記述されるものも登場しました。例えば、梶原性全(かじわら しょうぜん)の「頓医抄」、有林の「福田方」などで、著者の独自見解が盛り込まれた画期的なものでした。
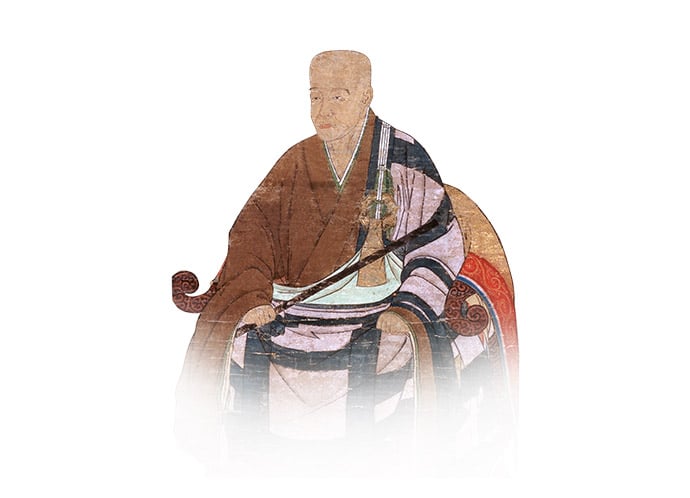
栄西(ようさい) (1141~1215)
栄西はわが国臨済宗の開祖。1168(仁安3)年入宋、1187(文治3)年再入宋し、5年後帰国。臨済禅を伝えた。1199(正治元)年、鎌倉に寿福寺を、1202(建仁2)年には京都に建仁寺を建立。

梶原性全(かじわら しょうぜん) (1266~1337)
鎌倉時代の名僧医、浄観と号す。1303(嘉元元)年『頓医抄』50巻、1315(正和4)年『萬安方』62巻を著した。
参考画像:【栄西】建仁寺両足院 所蔵
-
1336〜 室町時代
詳しく見る中国伝統医学の日本化
中国の李朱医学を日本に持ち帰る
室町時代後半から江戸時代前期は、中国伝統医学の日本化が始まった時期です。田代三喜(たしろ さんき)は、当時の中国で最先端医学であった金元医学、特に李朱医学を日本に持ち帰りました。
田代三喜の弟子の曲直瀬道三(まなせ どうざん)は医学校(啓迪院)をつくり、一説には3000人にのぼる門弟を抱えていたとも言われ、医学が日本各地に広がっていくことになります。
田代三喜(たしろ さんき) (1465~1537)
武州越生(一説に川越)の出身。渡明して日本人僧の月湖に金元流の医学を学び、帰国後、鎌倉円覚寺、足利を経て古河に移り住み、「古河の三喜」として名声を博したと伝えられる。

曲直瀬道三(まなせ どうざん) (1507~1594)
京都の出身。幼くして僧籍に入る、相国寺に居したが、1528(享禄元)年関東足利学校に入り、正文伯に師事して、漢学を修めた。
同4年、田代三喜に会って医学に転じ、李朱医学を学び、李朱医学を日本の実情に適合させ広めた。
1545(天文14)年京に帰り、医学舎啓迪院を創建し門人を育成。時の権力者、足利義輝・毛利元就・織田信長・豊臣秀吉や天皇家の信任を得、その医療を担当した。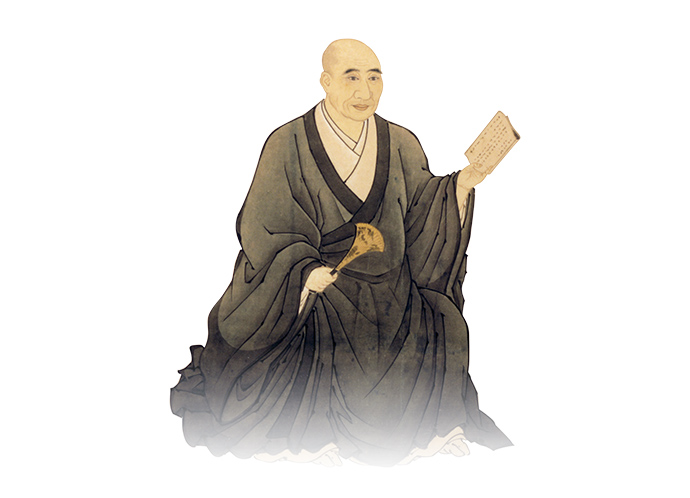
参考画像:【田代三喜】【曲直瀬道三】 財)武田科学振興財団 杏雨書屋 所蔵
-
1603〜 江戸時代
詳しく見る日本の伝統医学・漢方の始まり
古方派 「傷寒論」と「金匱要略」への回帰を唱える
1600年代後半になると、中国医学の日本化が一気に進行していきます。
それ以前の金元医学に基づく陰陽五行説を中心とした観念的な理論が、現実の治療にそぐわないとする医師が現れ、実践的な「傷寒論」「金匱要略」を支持する医師が登場します。とくに「傷寒論」は、病気の進行に合わせた病態が記され、それに対応する処方が記されています。病気の進行度と病態を見極めれば、対応処方が分かる実践的な医学書です。
この時代は実践的・実証的な考え方が広がり、例えば、山脇東洋(やまわき とうよう)が人体の構造を理解するために日本初の解剖図誌を著しました。また、吉益東洞(よします とうどう)は臨床経験を踏まえて「傷寒論」「金匱要略」を独自の見解に基づいて処方別に再編成し、「類聚方(るいじゅほう)」を著しました。
このような医師たちを、「傷寒論」「金匱要略」という古典への回帰を唱えたことから「古方派」と呼んでいます。名古屋玄医(なごや げんい)(1628~1696)
京都に生まれる。古方派の始祖。中国医籍を読破し、数々の著作をなした。『傷寒論』『金匱要略』の説を敷衍し、古典の重要性を説く。
後藤艮山(ごとう ごんざん) (1659~1733)
わが国の古方派の祖とされる。一気留滞説を提唱、百病は一気の留滞によって生じるとし、治療の綱要は順気をもってした。香川修庵、山脇東洋ら多くの門人を育てた。
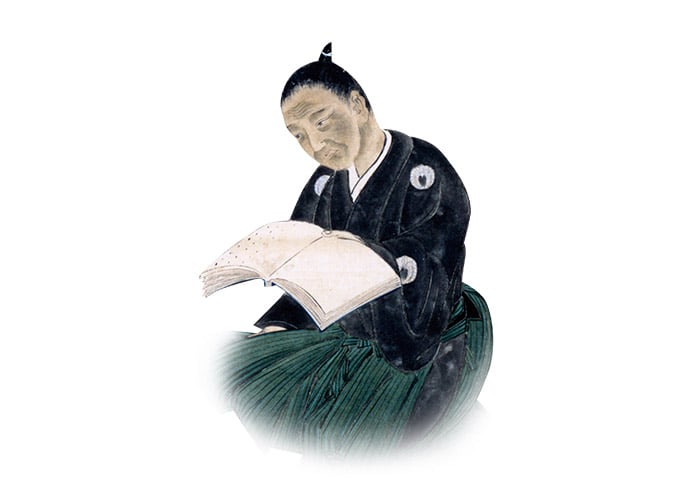
山脇東洋(やまわき とうよう)(1705~1762)
養祖父の山脇玄心は曲直瀬玄朔の弟子。東洋は後藤艮山に学んだことから古医方を重視。東洋は1754(暦4)年閏2月7日、官許を得て京都六角獄舎で処刑された屍体を解剖させ、門人の浅沼佐盈に観臓図を作成させた。
『蔵志』はこの記録を公刊したものであり、わが国解剖図誌の嚆矢として歴史的意義が大きい。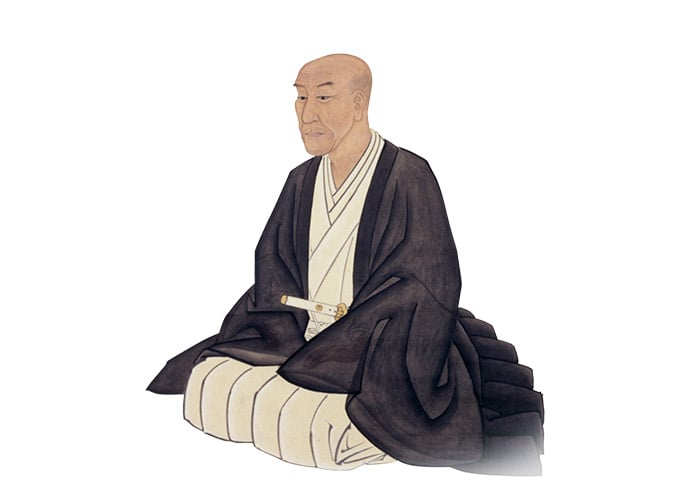
吉益東洞(よします とうどう)(1702~1773)
19歳で医を志し、のち曽祖父の吉益姓を襲った。張仲景の医方の研究に傾注し、1738(元文3)年京都に上り医を行い、40歳過ぎて山脇東洋に認められてからは大いに名声を博し、古方派の雄として当時の医界を煽った。
主著に『類聚方』『薬徴』『方極』『古書医言』などがある。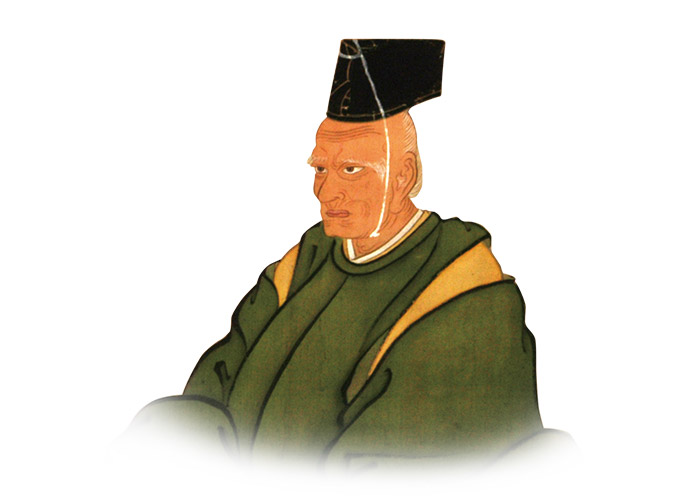
吉益南涯(よします なんがい)(1750~1813)
南涯は吉益東洞の長子で京都の生まれ。名は猷、字は修夫、号ははじめ謙斎のち南涯。
1773(安永2)年父の跡を継ぎ、医業大いに栄えた。
1788(天明8)年の大火で大坂に移ったが、数年後京都三条東洞院の旧地に復した。腹診法を確立、気血水説を提唱した。
尾台榕堂(おだい ようどう) (1799~1870)
信濃魚沼郡医家小杉家の4男として生まれる。16才の時、江戸に出て尾台浅嶽について東洞流古方を学んだ。浅嶽の死後、師家を嗣ぎ、診療を継続した。
浅田宗伯とともに幕末の江戸の二大名医として称えられた。吉益東洞に傾倒し、生涯東洞流医術を実践した。多くの門人を育成し、また著作多数。参考画像:【後藤艮山】【山脇東洋】財)武田科学振興財団 所蔵 【吉益東洞】【吉益南涯】 エーザイ(株)内藤記念くすり博物館 所蔵
日本漢方の発展・独自化の達成
多くの学派の登場
江戸時代の後期には、古方派が極端な主義をとった反省から処方の有用性を第一義とし、臨床に役立つものなら学派を問わず、経験的・臨床的に良所を享受する柔軟な姿勢をとる考証学派、折衷派、オランダから伝来した西洋医学を取り入れた漢蘭折衷派など、多くの学派があらわれます。
幕末になると、「漢方界の巨頭」と言われた浅田宗伯(あさだ そうはく)が将軍の診断を行う幕府のお目見え医師になり、明治維新後は皇室の侍医(明治天皇の治療)として漢方診療を行いました。詳しく見る考証学派
臨床に役立つものなら学派を問わず、経験的・臨床的に良所を享受する柔軟な姿勢をとる学派

多紀元簡(たき もとやす)(1755~1810)
父の多紀元悳に医を学んだ。松平定信の信任を得て1790(寛政2)年、奥医師・法眼に進んだ。翌年、躋寿館が幕府直轄の医学館となるにともない、助教として幕府医官の子弟を教育。
従来の古典解釈を反省し、漢方古典を文献学的、客観的に解明しようとした。
多紀元堅(たき もとかた)(1795~1857)
江戸後期の幕府医官。元簡の第5子で、はじめ浅草に住み、のち日本橋に邸を賜る。元簡の家督は兄元胤が継ぎ、元堅は別に一家(多紀矢の倉家)を興した。
父の考証学の学風を継いで善本医籍の収集、校訂、復刻に努め、渋江抽斎、森立之、小島尚真(宝素)らの考証医学者を育てる。
彼らの研鑽は特に書誌学の面において中国をはるかに凌ぐ成果を生んだ。
参考画像:【多紀元簡】【多紀元堅】 財)武田科学振興財団 所蔵
詳しく見る折衷派
処方の有用性を最重要視し、後世方派と古方派の良所を折衷した学派。

和田東郭(わだ とうかく) (1744~1803)
摂津高槻の人で、1797(寛政9)年法橋。1799(同11)年には法眼に進む。 臨床に長け、腹診を重視した。優れた臨床の手腕を発揮。

原南陽(はら なんよう) (1752~1820)
水戸藩医の家に生まれ、京都に遊学して山脇東門や産科の賀川玄迪に学び、江戸で開業。のち父の跡を継いで水戸藩医となって臨床、学問に腕をふるった。
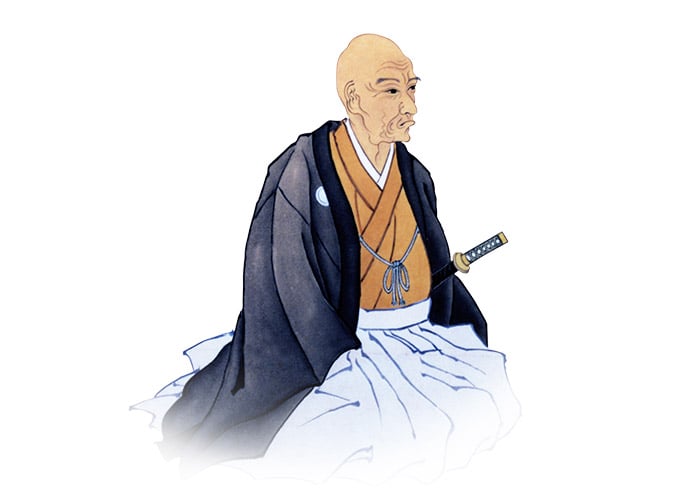
浅田宗伯(あさだ そうはく) (1815~1894)
信濃筑摩郡出身。中村仲・中西深斎に医を、猪飼敬所・頼山陽に文を学んだ。江戸で名医・名儒と交わり、臨床医として名声を博した。幕末にはコレラや麻疹の治療に腕をふるい、幕府の御目見医師に抜擢され、1865(慶応元)年幕命を受け、横浜駐在中のフランス公使レオン・ロッシュの治療に成功。法眼に進んだ。
維新後は皇室の侍医として漢方をもって診療にあたり、漢方医学の存続に尽力した。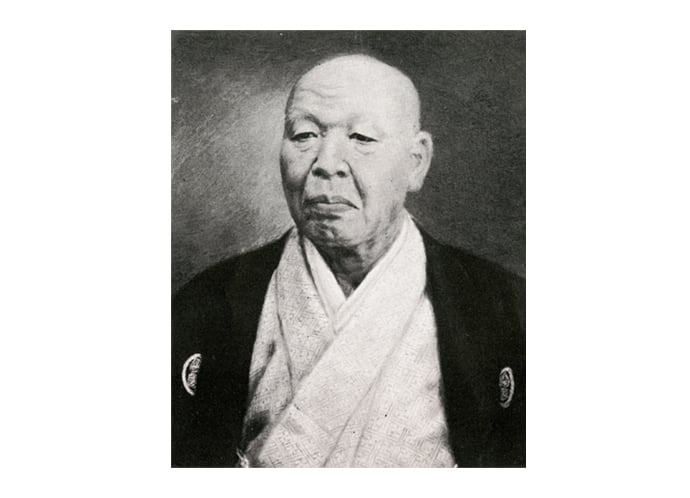
参考画像:【和田東郭】【原南陽】 財)武田科学振興財団 所蔵 【浅田宗伯】 北里大学東洋医学総合研究所 医史学研究所 所蔵
詳しく見る漢蘭折衷派
漢方と蘭方の利点をそれぞれ取入れ、独自の医術を実施した学派。

華岡青州(はなおか せいしゅう) (1760~1835)
京都で吉益南涯、大和見立に学び、漢蘭折衷の外科術を研究。1804(文化元)年、自己の開発した麻酔剤(通仙散)を用いて世界で初めて乳癌摘出手術に成功した。青洲の門人は千人を超えたというが、青洲自身は著述を行わず、その医術は門人の筆記により、写本として広く流布した。
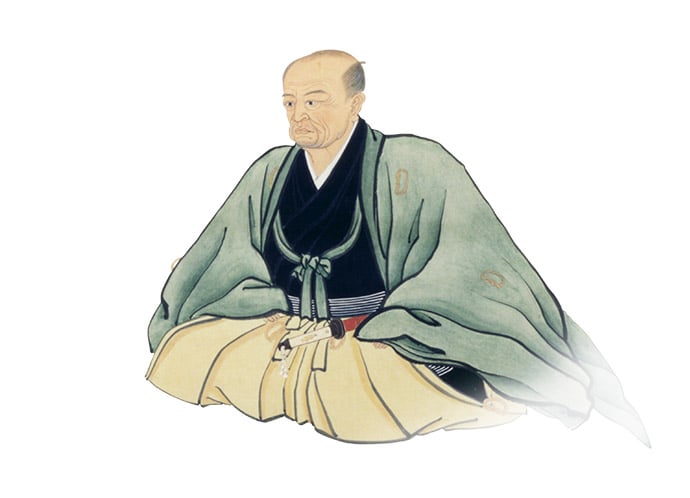
本間棗軒(ほんま そうけん) (1804~72)
水戸の人で、漢方を原南陽に、蘭方を杉田立卿に修学。さらに経学を大田錦城に学び、長崎に赴いてシーボルトに就き、京都では高階枳園、紀州では華岡青洲門で学んだ。
江戸で開業して華岡流医術を行い、はじめて大腿切断手術に成功。水戸藩医、水戸医学教授となった。著書に『内科秘録』『瘍科秘録』などがある。
参考画像:【華岡青洲】【本間棗軒】 財)武田科学振興財団 所蔵
詳しく見る蘭方
オランダを交易国としており、当時日本に伝えられた西洋医学。

シーボルト(1796~1866)
現在のドイツ、バイエルン州の医師の家に生まれる。ヴェルツブルグ大学医学部、動植物学、民族学なども学ぶ。
1823年出島オランダ商館医として来日。日本に近代西洋医学を伝え、日本の近代化や、ヨーロッパでの日本文化の紹介に貢献した。
緒方洪庵(おがた こうあん)(1810~1863)
備中足守の出身、江戸にて宇田川玄真に蘭学を学ぶ。長崎に遊学、大阪瓦町に蘭学塾を開く。後に北浜に移り、適塾と称する学問所を開き、多くの逸材を輩出した。
種痘法の導入、普及に努力した。のち幕府に召され、法眼となる。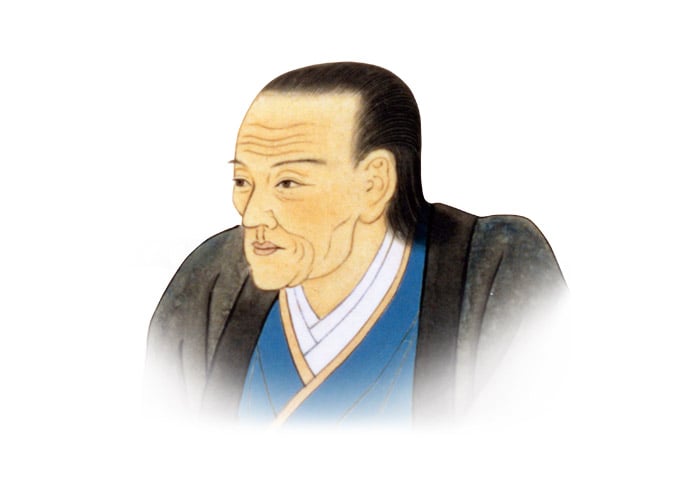
参考画像:【シーボルト】 長崎歴史文化博物館 所蔵【緒方洪庵】 財)武田科学振興財団 所蔵
-
1868〜 明治~
大正時代衰退・存続
明治時代 西洋医学が台頭し、漢方医学が衰退
富国強兵を目指す明治政府は、ドイツ医学中心の新しい医学制度「医制」を制定し、試験制度を採り入れ、医業の開業許可を制度化します。1883年には、国家試験に合格しなければ医業開業が許可されない医師免許制度が制定されました。
これまでは、浅田宗伯のような漢方医に弟子入りし、技量が身についたところで医業開業ができたのが、漢方医学のみを習得していては開業できない時代になったのです。詳しく見る国会第8議会にて漢医継続願が否決される
浅田宗伯など漢方医は漢医継続願を提出しますが、1895年に国会で否決され、漢方医学は衰退の時代に入ります。しかし明治政府は、医師免許を取得した医師が漢方薬を使用して治療することを禁止した訳ではありませんでした。そのため漢方医学は一部の医師や薬剤師によって、脈々と受け継がれていきます。
1910年に和田啓十郎が『医界之鉄椎』を、1927年には湯本求真が『皇漢医学』を出版。これらの著述がきっかけとなり、昭和に入り漢方医学は再び注目を集めるようになりました。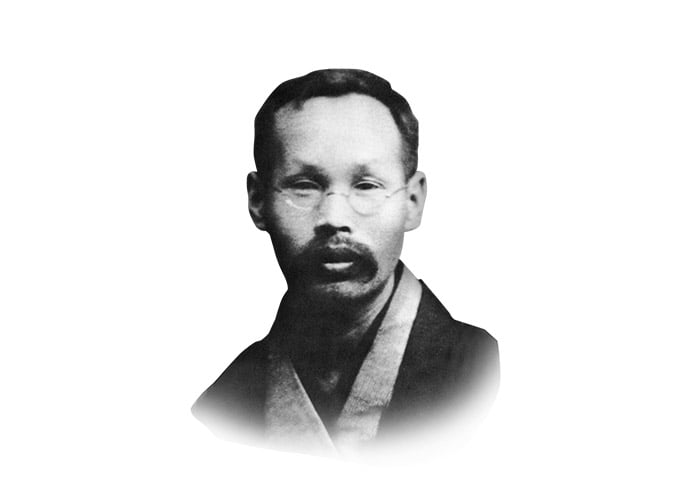
和田啓十郎(1872~1916)
1872(明治5)年長野県松代市に生まれる。幼少の頃、姉の難病を漢方医により治癒されたことから漢方医学を志す。1892年に上京し、済世学舎(現在の日本医科大学の前身)に入学し西洋医学を学ぶ。吉益東洞著『医事或問』に感激、漢方医多田民之助に師事。
1910年、苦労して南江堂より『医界之鉄椎』を千部、自費出版。大いなる反響を巻き起こす。
1915年、第2版を湯本求真の治験例を加え自費出版。1916年、45歳にて逝去。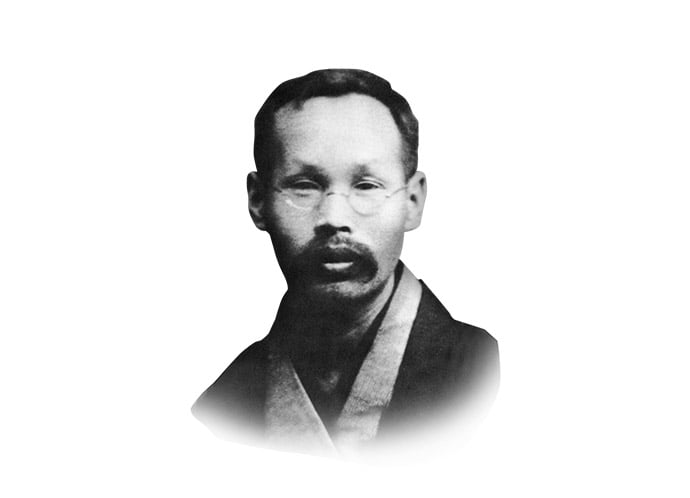
参考画像:【和田啓十郎】 北里大学東洋医学総合研究所 医史学研究所 所蔵
-
1926〜 昭和時代
復興
日本東洋医学会が設立
1950年(昭和25年)に、日本東洋医学会が設立されます。1950年代後半になるとサリドマイドなど相次ぐ薬害の発生などにより、西洋薬一辺倒を懸念する声が高まります。
-
1960
発展・進展
日本薬局方収載生薬が薬価基準に収載
1963年には、「調剤容易な配合剤は薬価基準には収載しないが、医療機関でこの種の配合剤を使用した場合には、既収載の単味製剤の合算により請求できるものとする」とする追補が出されます。
-
1967
漢方エキス製剤4処方が初めて保険適用となる。
-
1975
厚生省薬務局監修『一般用漢方処方の手引き』薬業時報社より刊行。
-
1976
医療用漢方製剤38処方が保険適用され漢方が医療現場によく知られるようになる。ツムラは医療用漢方製剤33処方が薬価基準収載。
-
1985
厚生省薬務局 「医療用漢方エキス製剤の取扱いについて」を通知。
-
1987
医療用漢方製剤147処方が改めて薬価基準収載。
-
1991
医療用漢方製剤の再評価指定。日本東洋医学会が日本医学会分科会へ(第87番目として)正式に登録。
-
2001
文部科学省が医学教育モデル・コア・カリキュラムを制定します。これは、医学部生が卒業時までに習得する内容を示したもので、この中の到達目標に「和漢薬を概説できる」という項目が採録されました。当時、全国の医学部医科大学は全部で80大学ありましたが、漢方医学のカリキュラムがあったのは半数以下でした。
その後2004年には80大学(現在は82大学)すべてで、漢方医学のカリキュラムが取り入れられることになります。 -
2002
文部科学省 薬学教育モデル・コア・カリキュラムに「現代医療の中の生薬・漢方薬」が採録。
-
2006
日本専門医認定機構により日本東洋医学会専門医が認定。
-
2017
文部科学省 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの「薬物及び薬物投与による人間の反応」に和漢薬(漢方薬)」が採録。
-
2018
文部科学省 歯学教育モデル・コア・カリキュラムの「薬物と医薬品」「薬物の適用と体内動態」「薬物の副作用と有害作用」に 薬物(和漢薬を含む)と採録。
